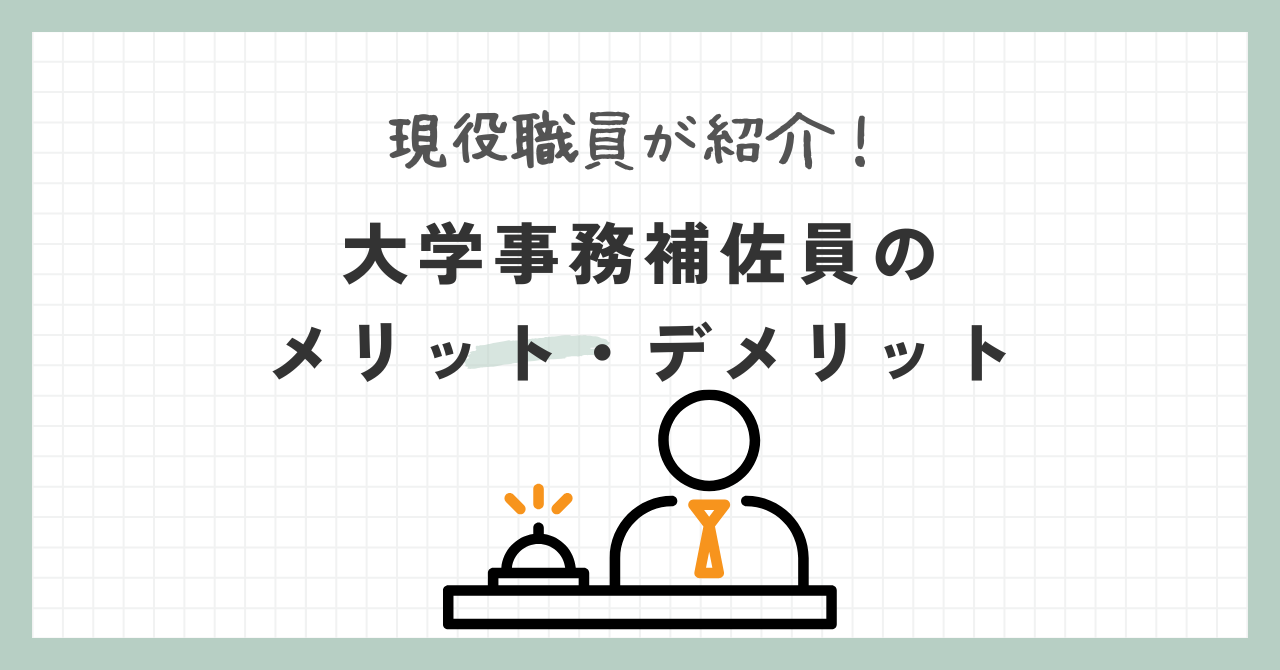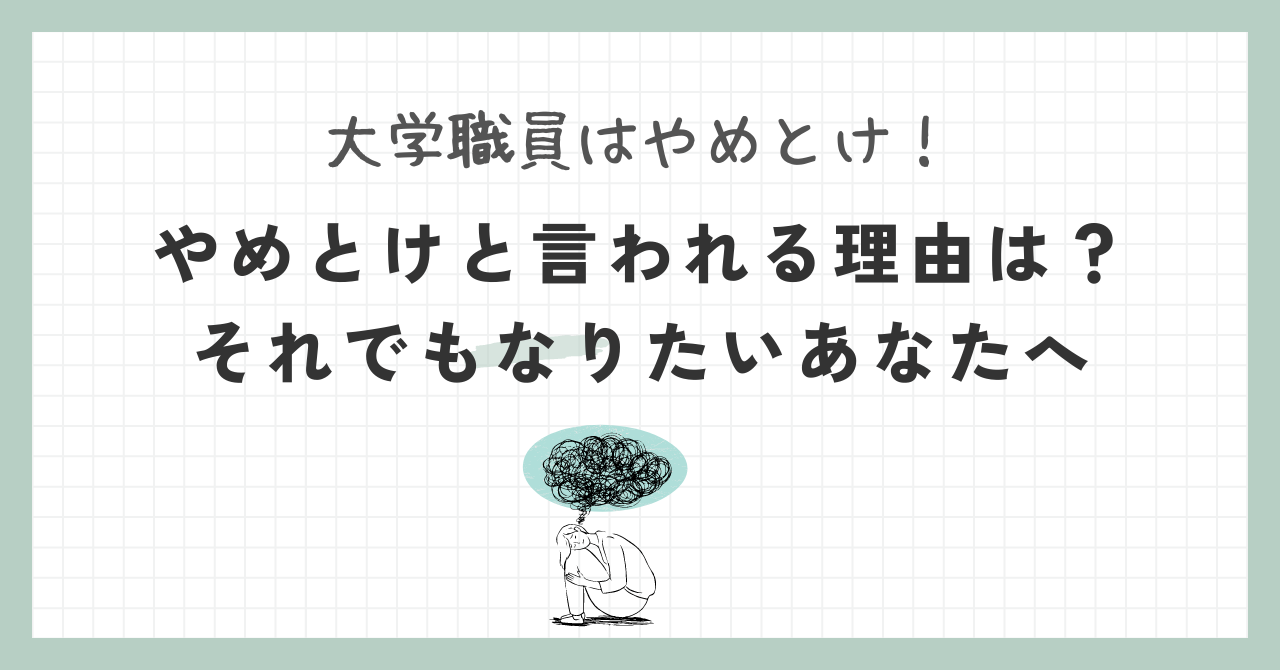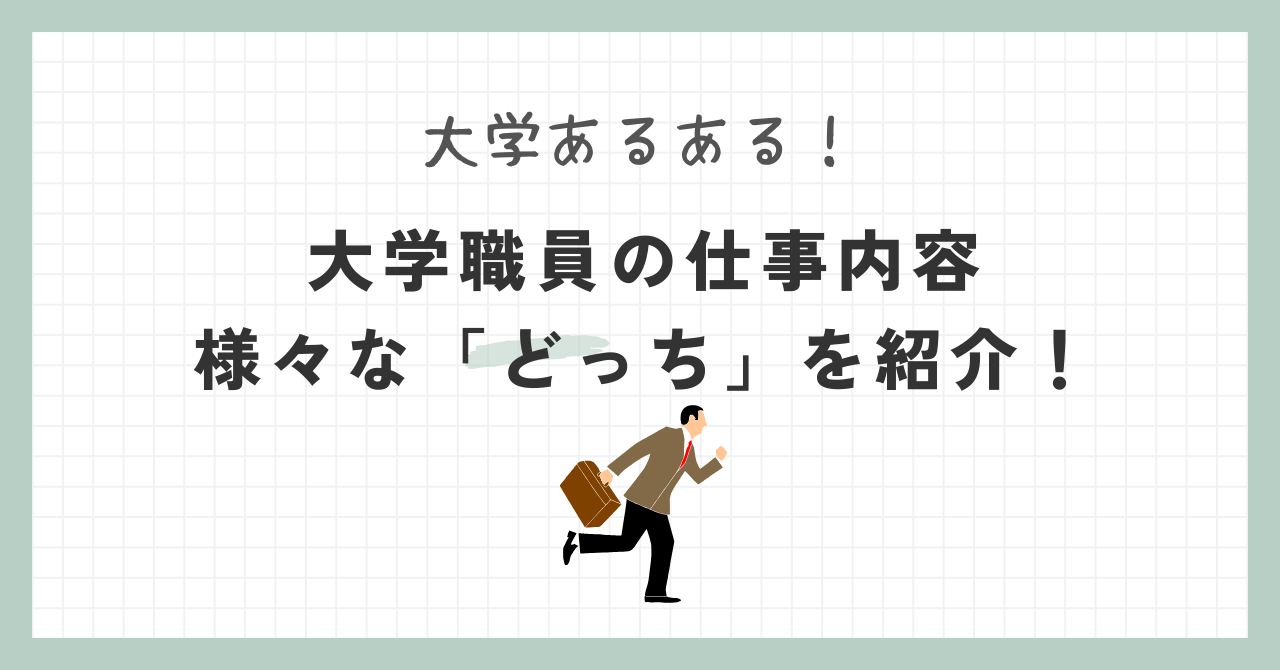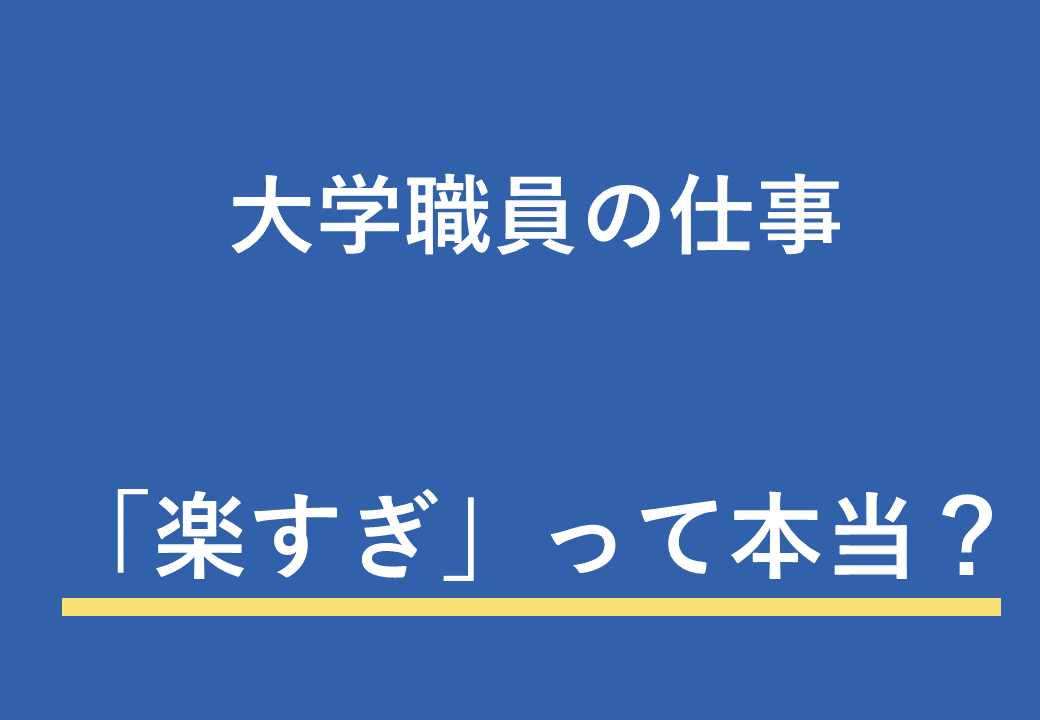大学業界で使われる用語一覧を紹介
A4).png)
大学に通ったことがある人は「自分は大学についてよく知っている」と思ってるかもしれません。
しかし、教職員でなければ聞かない業界用語もたくさんあるので紹介します。
実際に、ここで紹介する用語は私が大学職員に入職するまでは知らなかった言葉がほとんどです。大学業界研究に役立ててください。
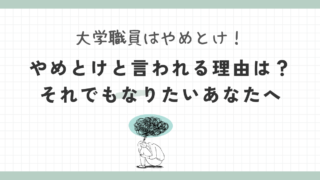
研究費関係の用語

かつて大学教員には莫大な研究費が配分されていました。国際的な競争力のために、予算が組まれていた時代です。
それが2000年前後から状況が変わり、国から大学に交付される研究費が減らされ始めます。
その後は民間企業と協力したり、自ら研究助成の公募に応募したりして、研究費を獲得する必要がでてきました。
1人あたり年間100万円以上あった研究費が、10万円ほどまでに減っている大学・学部もあります。
大学を取り巻く状況として、以下の状況を理解しておくとよいでしょう
- 国から措置される使用用途自由の運営費交付金は減少傾向
- 成果や競争が必要な研究費の獲得に力を入れている
- ネーミングライツ、施設貸出などで収益を上げている大学もある
運営費交付金
運営費交付金(うんえいひこうふきん)は、国から支出されている大学が運営するための資金です(資金使途は比較的自由)。この中から、人件費・学生が利用するため設備費・大学教員に配分される研究費(の一部)などが賄われます。
国からの運営費交付金は年々減っており、成果に応じた予算の配分なども行われています。国から措置される予算が減っているため、運営費交付金以外の予算確保に大学は力を入れています。
科学研究費補助金
科学研究費補助金=科研費(かけんひ)は、運営費交付金が削られる代わりに国が支出を増やした項目です。
大学教員は定額で配分される運営費交付金が減ったため、科学研究費補助金を獲得しなければ研究費が減ってしまう状況になっています。
科研費の採択率は約30%で、10件中3件の申請が採択されます。採択されるためには「国や国民の社会生活を向上させるための研究を行うために研究費が必要」と示す申請書を作成するのがポイントです。
申請書作成の補助を大学職員が行っています。
受託研究費・共同研究費
大学は民間企業などからお金を獲得してくることにも力を入れています。
受託研究は企業などからある実験・調査等を委託されて、大学が研究を行います。
例えば、ある食品の健康への影響を食品メーカーが大学に委託するケースがあります。これで、企業が大学に委託費を支払います。
共同研究は企業と大学がお互いの研究者と研究施設などを使って研究を行うものです。
先程の例で言えば、食品メーカーと大学がお互いに研究員等を提供しあうことになります。
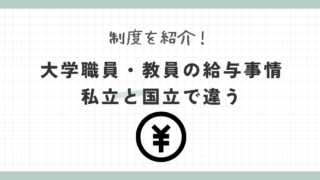
論文関係の用語

大学教員の評価を決める1つに「研究費の獲得」がありますが、もう1つの重要な評価項目が「執筆論文の質と量」です。
社会的影響力の大きい論文をたくさん書くことが大学教員には求められます。
大学職員として意識すべきことは以下のようなことです。
- 研究に関する専門的な知識ではあるが、最低限の知識はあったほうがいい
- 業績調書を見て、先生と話ができるようになるとベター(人事担当・研究推進担当)
インパクトファクター(=IF)
論文の質を決める1つの指標がインパクトファクター(=IF)と呼ばれる指標です。インパクトファクターは学術雑誌の影響力を表す数値です。
掲載されている論文が1年平均何回、引用されたかを示す数字(過去2年間の平均値)がインパクトファクターです。
2025年のインパクトファクター=2023~2024年に掲載された全論文の被引用回数÷2023~2024年の掲載論文総数
世界的に有名な化学誌の『Nature』で50程度のインパクトファクターです(年度により変動あり)。
分野にもよりますが、インパクトファクターが10を超える雑誌への掲載は素晴らしい実績といえるでしょう。
インパクトファクターの高い雑誌への投稿が多ければ、社会的影響力も高く、素晴らしい研究をしている教員と評価されます。
トップ10%論文
インパクトファクターは雑誌のレベルを示すものになります。一方で、論文ごとにも評価される基準があります。同分野の中で引用された回数を比べるものがトップ10%論文です。
同分野で上位10%に入るものは「トップ10%論文」と呼ばれています。インパクトファクターは分野ごとに引用されやすさが異なるため、トップ10%論文で評価したほうが分野差がでないと言われます。
トップ10%論文を多く書いている研究者はその分野で優秀な研究者であることがわかります。
ファーストオーサー(筆頭著者)
研究者は「履歴書」とともに「業績調書」を作成しています。どのような研究費を獲得しているか、論文を書いているかを示すものです。
その中で、論文については記載のルールがあり、執筆者・題名・雑誌名・ページ数などを記載します。
1つの論文に複数の著者が名前を連ねることが多いですが、その先頭に記される著者をファーストオーサー(筆頭著者)といいます。その論文について、メインの執筆者となっている人です。
ファーストオーサー(筆頭著者)の論文を多く執筆している研究者のほうが評価は高くなります。
また、コレスポンディングオーサー(責任著者)という用語もあります。「実質責任著者」とも言われます。
大学院生が書いた論文などでは、学生が筆頭著者として論文を書いて、監修した指導教員がコレスポンディングオーサーとなることが多いです。
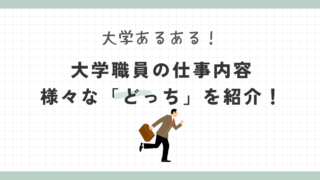
資格に関する用語

大学の教員には誰でもなれるわけではありません。
基本的には学部・大学院ごとの教授会で資格審査を受ける必要があります。資格審査に合格することで、授業を担当したり、研究指導をしたりできるようになります。
合・○合資格
大学教員が学生を指導するための資格が「合・○合資格(ごう・まるごう)」です。
文部科学省が「大学教員が学生を指導(論文指導)する場合には合・○合資格がある場合に限る」としています。
指導教員となれるのが「○合」資格、指導を補助できるのが「合」資格です。
博士前期課程の大学院生を指導できて、博士後期課程の大学院生の指導を補助できる場合は「前期○合・後期合」資格と表現します。
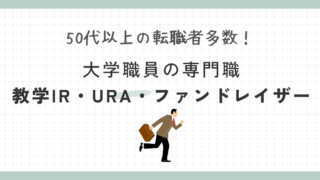
非常勤講師資格
非常勤講師として登壇する場合も資格の審査が行われています。
そもそも大学を設置する際に、全ての授業科目および担当教員も文部科学省に届け出ています。
文部科学省に届け出る前に、大学内で資格があることを審査しているわけです。
学部の教授会などで、「履歴書・業績調書」などを用いて資格審査を行っています。当該分野の博士号を持っている、当該分野での勤務歴が5年以上あることなど、学部ごとに基準を設けて非常勤講師としての資格審査を行っているケースが多いです。
会議に関する用語

大学は文部科学省から設置認可を受けて、教育機関として存在しています。
国からの認可を受けている機関ですので、民主主義のルールに従って議決を行わなければなりません。そのため、多くの会議体があります。
役員会・経営協議会
大学の運営に関する重要事項を決定します。
大学も公的機関とはいえ、財務収支があります。財務収支の赤字が続くと倒産もありえます(実際には国からの、再建支援金等が出てすぐに潰れることはないでしょうが)。
財務状況等の重要事項について、学長や理事が検討するのが経営協議会です。大学によって会議の名前は異なります。
各会議体は以下のように、規程が定められ、規程に基づき運営されています。
教授会
経営協議会など、大学全体の会議もありますが、細かなことは各学部ごとの教授会で審議が行われます。
学部の教授等の教員が構成員となって、学部の運営・方向性を検討します。
大学教員にとっては学部長等の役職にならなければ、経営協議会はあまり関係なく、教授会が最も大きな会議になります。
入試委員会・学生委員会
教授会は学部内の全教授が構成員となっていますので、そこで議論をしてもまとまりがつきません。
そこで、教授会は内容に応じて、各委員会などに案を作成してもらい、それを教授会で決定しています。
例えば、入試の方針やオープンキャンパスの計画などは「入試委員会」、サークル活動への支援金や学生の懲罰に関することは「学生委員会」などです。
委員会の所属が多い教員は学内会議だけで、週に3.4回あるという教員もいます。
履修案内・履修登録に関する用語

大学に入学すると「履修案内」をもらいます。これは学部や学科ごとに異なり、授業を受講するためのルールブックのようなものです。
- 1年生のときに「〇〇」と「〇〇」という授業を履修すること(必修)
- 卒業までに124単位の取得と、卒業論文の提出が必要
- 教員免許を取得したい方はこの科目を履修すること
履修案内を読みながら、教務システムにアクセスし、履修登録を行います。アカウントとパスワードを使ってアクセスし、学期の初めに受講したい授業を登録していきます。
シラバス
履修案内とあわせて、確認するのが「シラバス」です。シラバスは授業内容を詳細に記しているもので多くの大学ではWEB上でシラバスを閲覧できます。
- 「授業科目名」
- 「授業を履修することの目的」
- 「各回の授業の内容」
- 「成績の付け方」
- 「備考:注意点」
このようなことが記載され、授業を履修することでどんなことが学べるのかがわかります。
授業科目・成績
授業科目は高校の頃とは異なり、具体的な内容になっています。「理科」「数学」などではなく、「昆虫を科学する」「代数学Ⅱ」などです。
この科目毎に試験等があり、科目毎に成績がつきます。
基本的には成績は「秀・優・良・可・不可」でつけれらます。高校までの5段階評価と同じように考えてもらえればよいと思います。
単位
大学の授業を履修し、成績がつくことを「単位を修得する」という言い方をします。
「単位」は「その授業科目を45時間相当勉強したもの」に与えられるとしています。
正式な勉強時間数を大学で管理しているわけではなく、「大学で勉強した時間数」+「自主学習した時間数」を相当して45時間の学習時間を確保することとされています。
この単位を定められた数だけ修得することで、卒業することが可能になります。
多くの大学は124単位を卒業要件単位としており、単純計算すると5580時間が卒業までに必要となりますね。
時間割
シラバス・履修案内を見て、履修したい授業が決まったら、時間割を確認します。
大学では自分で時間割を決めることができますが、開講している授業時間に合わせて組み合わせていく必要があります。
履修したい授業が同じ曜日の同じ時間に重なるということは大学あるあるです。その場合は、どちらかの授業を諦めるか、来年に回すという手もあります。
授業内容には興味ないけれど、単位を修得するために、空いている時間に時間割を見て授業を履修するということもあります。
単位・時間割・履修登録など、学生視点での大学に関する情報は姉妹サイト「教務.com」にまとめています。気になる記事があれば読んでみてください。
【関連記事】GPAの平均は2.4~2.8で3.0以上は上位20%!目安も紹介
【関連記事】大学生への懲戒処分の基準と事例!厳重注意・戒告・謹慎・停学・放学の違い
【関連記事】大学には最大何年までいられる?在学期間・在籍期間の計算方法
【関連記事】大学を留年したら費用はいくらかかる?奨学金は打ち切り?
学部・学科のルール

学部・学科ごとに細かいルールがあり、履修案内の冊子などに記載されています。
必修科目・選択科目
学部・学科ごとに受講しなければならない授業科目があります。これが「必修科目」です。
複数の中からどれかを選択して履修すればよいものが「選択科目」です。
必修科目は修得しなければ、卒業できませんし、他の科目の基礎となる考え方を学ぶことも多いため、優先的に学習・履修するのがいいでしょう。
進級要件・卒業要件
学部のルールの中に「進級要件・卒業要件」も決まっています。「1年生終了時に20単位以上習得していれば、2年生に進級できる」というようなものです。
また卒業要件も決まっており、全体の卒業要件単位数と分野ごとの必要単位などが定められています。

まとめ:業界用語を知っておくと面接に役立つ
大学業界ならではの用語を紹介してきました。
全てを覚える必要はありませんが、これらの言葉を知っていて自分なりの意見が言えると「しっかり大学のことを勉強してきているな」という印象を面接官に与えられます。
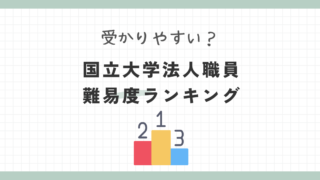
これから、国立大学法人の筆記試験受験を目指す方は以下の記事も参考にしてみてください。通信講座を利用すると効率的に試験対策ができます。