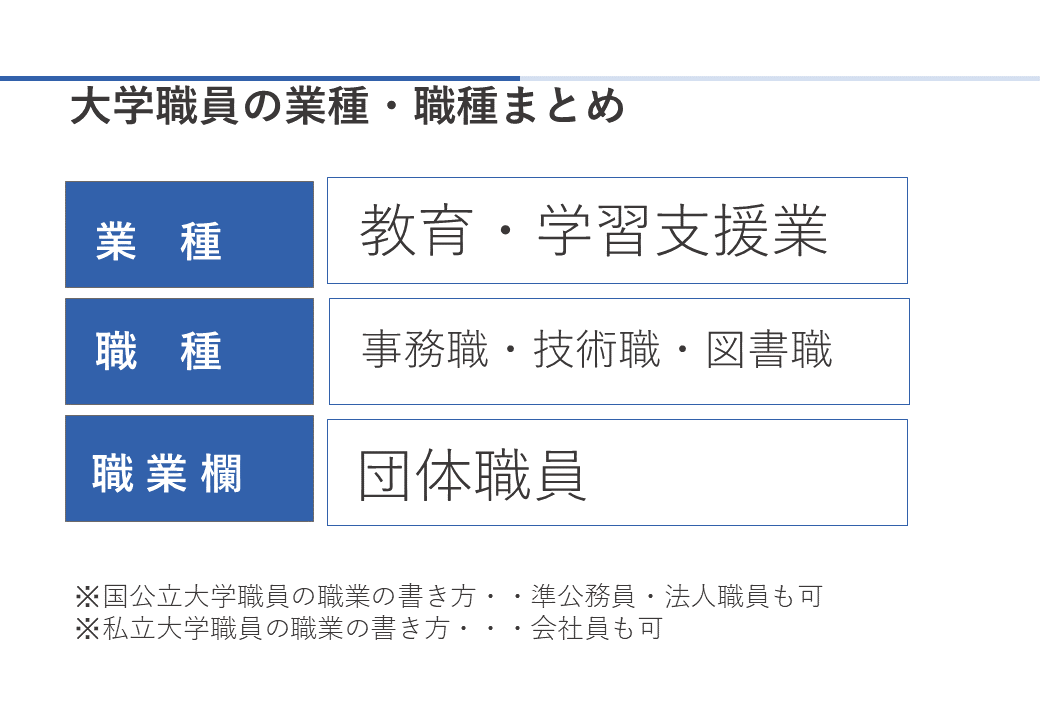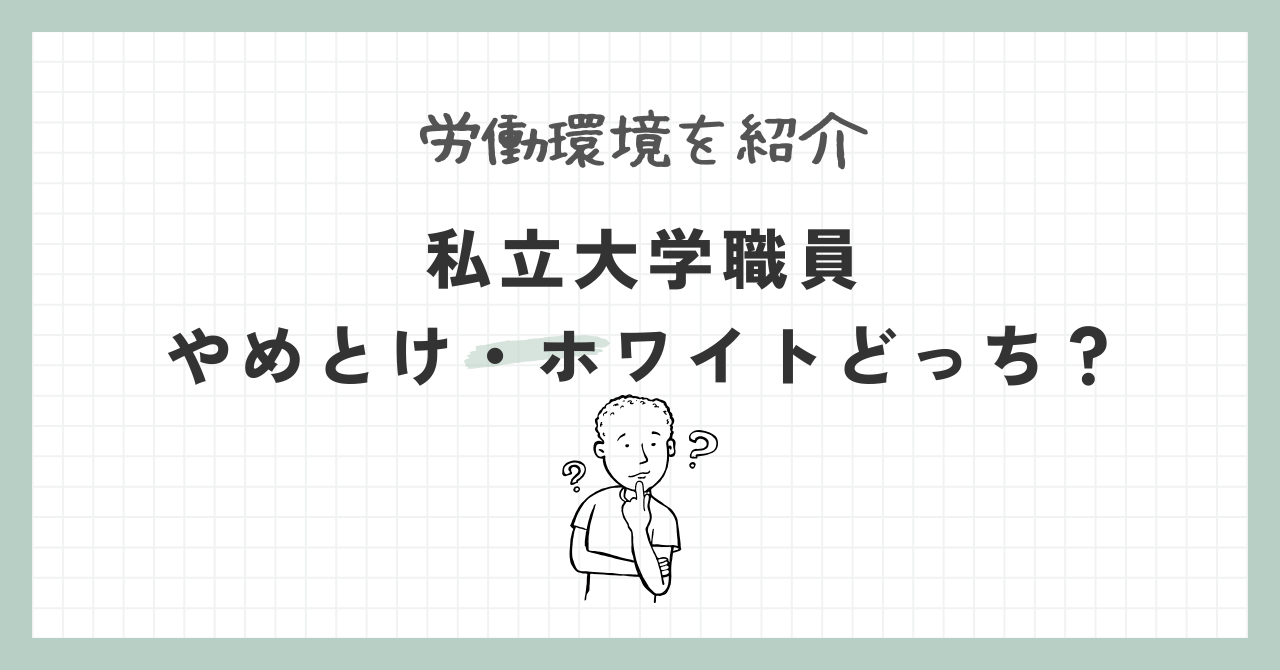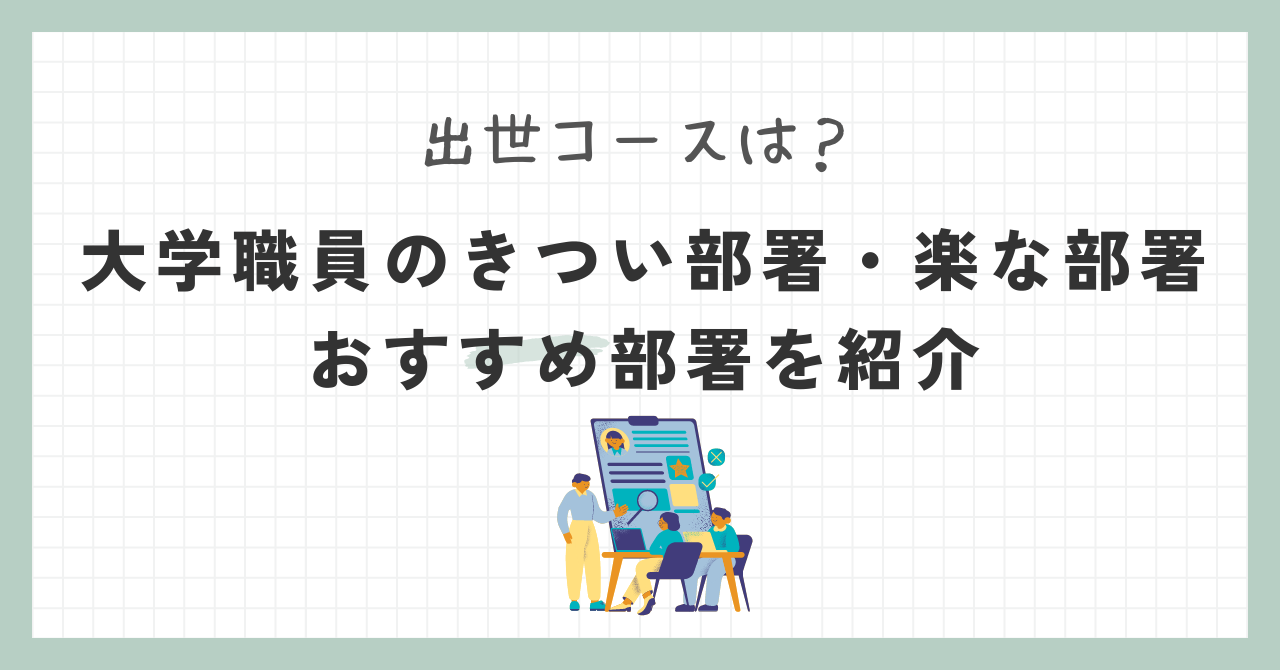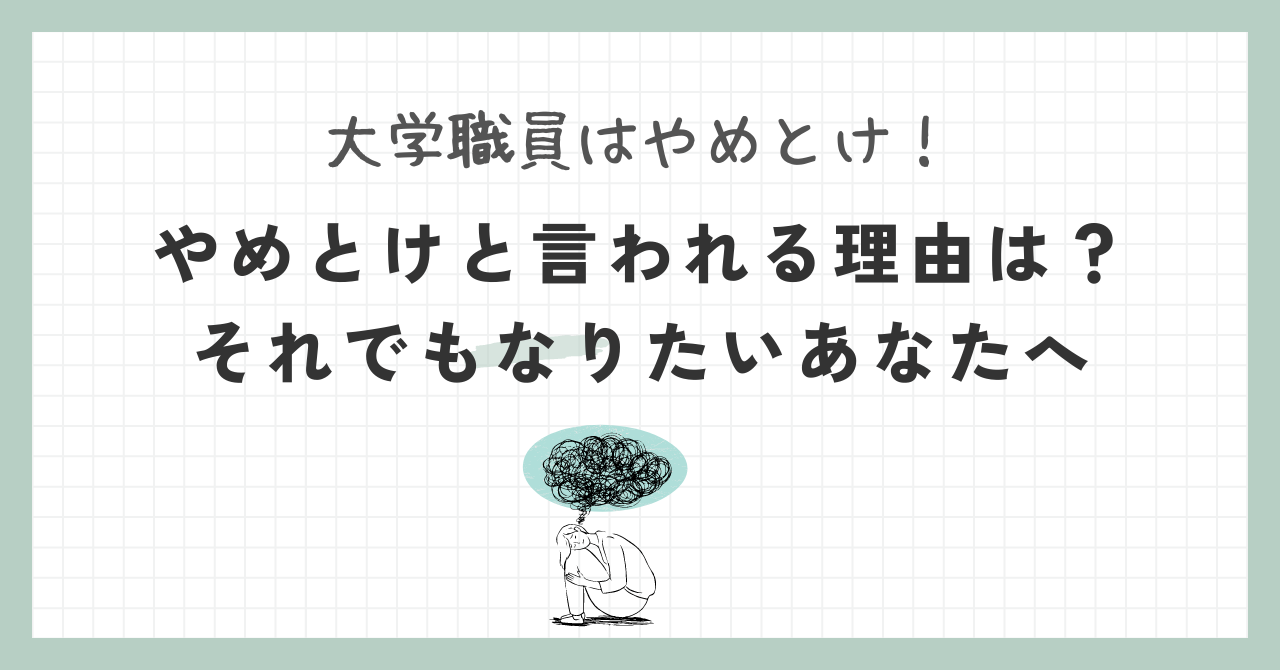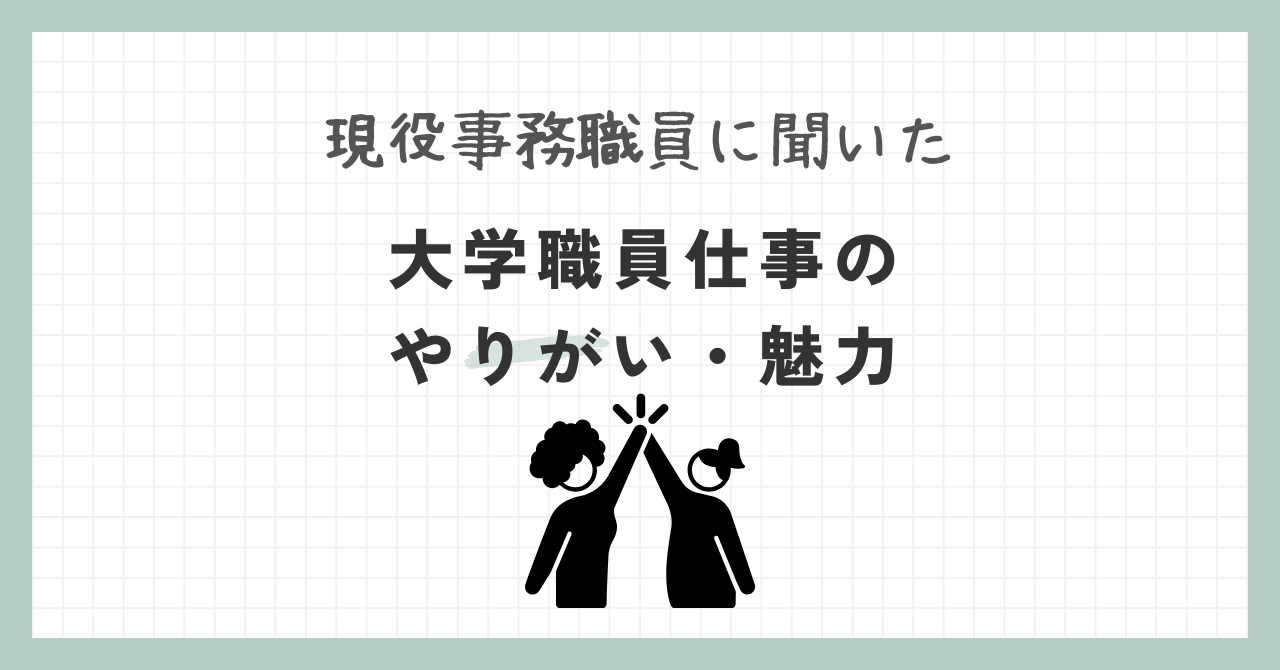大学職員の仕事内容を理解するのに必須!様々な「どっち」
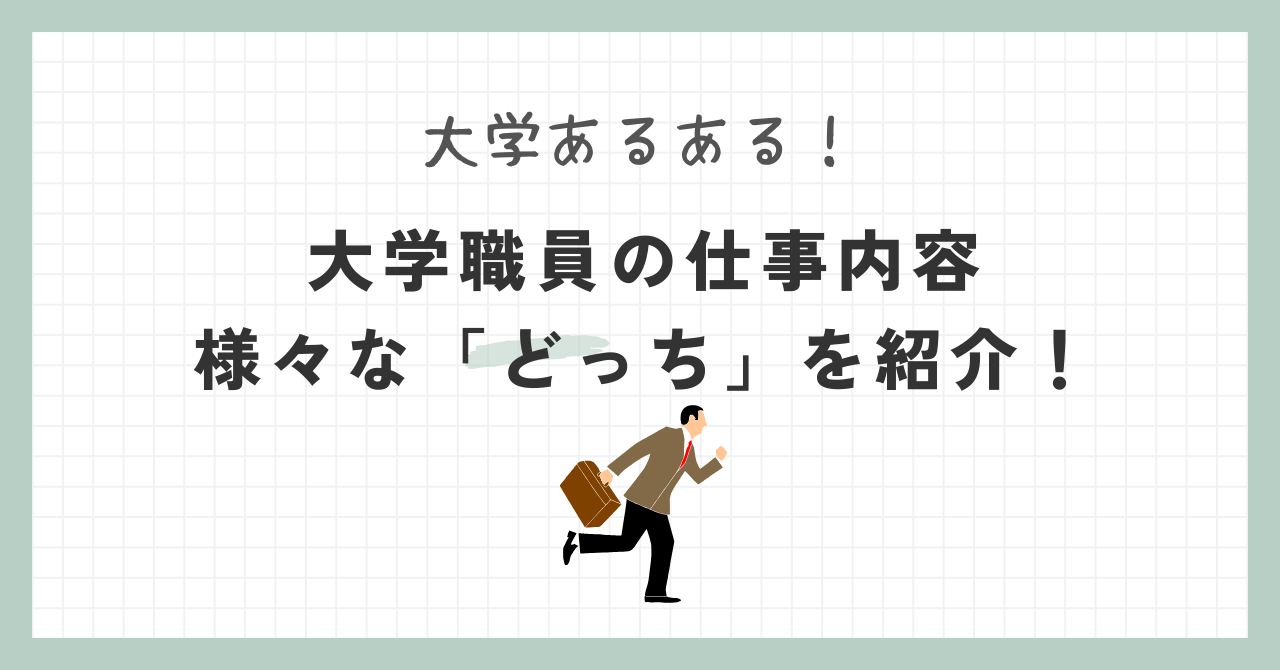
「給与」をとるか「やりがい」をとるのかなど、仕事を選ぶ際にどちらを選ぶか迷うケースは多いでしょう。
大学職員の仕事にも特有の「どっち?」と考えさせられるものが多くあります。
「専門職と総合職」「規程主義と現場主義」「業務の縦割りと教職連携」などです。
- 大学職員の仕事を理解するのに理解すべき様々な「どっち?」を紹介
- どちらがいいかは人によるが、自分の考えをまとめておくと面接で役に立つ
大学職員の仕事内容を深く理解するために、様々な「どっち?」があることを知っておきましょう。
本記事は、就職・転職の面接対策として、大学の課題を把握するのにも役立つと考えています。
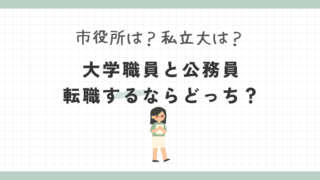
専門職と総合職どっち?
大学職員として新卒や第二新卒で就職する場合、様々な部署を異動する総合職的な採用がほとんどです。
一方で、大学経営の視点で考えると専門的な知識・スキルを持った職員が求められるケースが増えています。
- クラウド・AIなどの利活用や情報セキュリティの専門家
- 研究資源の有効活用を目指すURA(University Research Administrator)
- 寄附金集めができる営業を行う職員
一般的には若いうちには複数の部署を経験して、昇進とともに専門性を身に着けていくというキャリアプランを想定している大学が多いです。
ただ近年では、専門的なスキルが必要な職種には、非正規職員を採用している大学もあります。
総合職・専門職について、「どちらが偉い」「どちらを目指すべき」という明確な回答はできませんが、自分のキャリアプランについて考えておくと良いでしょう。
- 総合職として、係・課を統括する仕事をしたい
- 専門職として、大学の国際化に貢献したい
中途採用で、前職の経験を生かした専門職として活躍できる自信があるのであれば、専門性をアピールするのもありです。
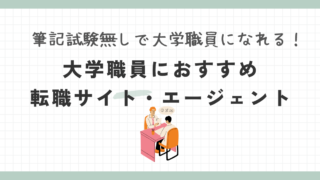
大学本部と部局窓口どっち?
大学職員の仕事は、大きく人事課・財務課などの大学本部と、学部・大学院ごとの部局窓口に分かれます。
一般的には、大学本部のほうが学長や理事などの近くで仕事をするため優秀な職員が配置され、部局窓口の仕事はないがしろにされる傾向があります。
一方で、教員・学生からの現場の意見を聞けるのは部局窓口です。現場の意見を聞かない頭でっかちな組織は、顧客離れが進んでいくと考えられます。
採用の面接官を務めているのは本部の職員が多いですが、大学本部で大学全体を見渡せる部署で働きたいか、現場に近い部局窓口で働きたいかは考えを整理しておく必要があります。
- 本部職員として、経営陣に近い場所で大学運営を学びたい
- 部局職員として、学生・教員の現場の意見を聞きながら仕事をしたい
本部・部局ともに人事異動で経験する可能性が高いので、「本部・部局で経験したことを異動先でも活かし、キャリアアップしていきたい」というのが模範回答になります。
規程主義と現場主義どっち?
大学では、民間企業より「規程主義」という考え方が強いように感じます。
- 規程に書いていないから認められない
- 例外を作る場合は、規程を改正する
- 定められた事項は定例的なことも、教授会での審議が必要
税金・補助金が多く注入されている大学では、公務員に近いような規程主義が重視されています。
一方で、困っている学生のために、無駄を省くために「現場主義的」な考え方が必要なこともあります。
- 規程主義・・・規定に則って、平等に仕事を進めていくべきという考え
- 現場主義・・・現場の状況解決を優先する考え
大学職員として活躍する人は、「規程・制度を理解しつつ、柔軟に現場が困らない仕事ができるように対応できる人物」だと考えています。
大学のミッションと利益追求どっち?
学校法人の存在は「教育」が第一目的のため、利益を追求するだけの組織ではありません。
利益を増やすのであれば、受験者を増やし、研究費を獲得することばかり考えればいいですが、学生の利便性・満足度も意識しなければなりません。
例えば、留学生を増やしてグローバル化を推進するというミッションがある場合にも、留学生を増やす広報活動ばかり行えば良いわけではありません。
- 多様な留学生を採用できる入試制度の確立
- 現役学生との交流機会の準備
- 日本語学習サポートの実施
利益追求にとどまらない、様々な施策を考える必要があります。
- ミッションを重視・・・大学の経営理念に立ち戻り、利益以外も重視
- 利益を重視・・・収入増・支出減・効率化などだけに注目
近年では、大学運営が厳しくなっているので、ミッションに財務状況の改善・向上を掲げる大学も多いです。大学には、「利益追求」と「教育研究」という2つの課題があるということを意識しておきましょう。
職員の仕事と教員の仕事どっち?
大学で働くのは主に教員と職員です。教員と職員の業務は主に以下のように分かれます。
- 教員・・・教育と研究
- 職員・・・大学運営に関わる各種事務
しかし、近年では教員の仕事とも職員の仕事とも言えない仕事が増えています。
- 学生の満足度の向上・・・専攻の学習であれば教員の仕事だが、課外活動のサポートは職員
- 入試広報・・・高校生への説明会などは職員の仕事だが、模擬授業など教員の協力も不可欠
- 研究活動の活性化・・・事務手続きが増えたため、専門的なスキルのある職員の支援が必要に
中堅以上の職員ではいまだに縦割りの意識が強い職員が多いですが、教職連携の意識の元、教員をサポートする姿勢が大学職員には重要だと考えます。
- 従来の職員の役割を重視し、事務方の仕事にまっとうする
- 職員の役割を広げ、教員の仕事を強固にサポートできる専門性を身につける
「従来の事務職員の役割だけでなく、積極的に教員の仕事をサポートする」というのが模範解答になります。
実際には、重要な決定時に体よく「教員に委ねる」というような、ずる賢さが必要な場面もあります。
形式知と暗黙知どっち?
形式知・暗黙知という言葉は、『大学職員のリアル』という書籍で私は知りました。
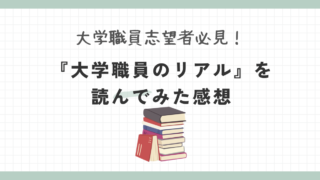
- 形式知(けいしきち)・・・規程やマニュアルなど決められた知識
- 暗黙知(あんもくち)・・・個人の経験等に基づく、言語化の難しい知識
規程主義と言われる大学職員の仕事でも、暗黙知は非常に重要です。
- 個人情報であるが、内々に〇〇課にデータを共有する
- 〇〇先生と〇〇先生は、仲が悪いため要注意
- 関係部署への事前の根回し
学内に知り合いが多く、暗黙知を上手に使って仕事をしている職員は重宝されます。
一方で暗黙知はあくまで学内だけで重要なローカルルールのため、学外や学部外では全く役に立ちません。転職を含めたキャリアを考えた場合には、形式知を積み上げることが重要です。
国公立大学と私立大学どっち?
国公立大学と私立大学の、仕事内容や待遇面での違いはよく話題になります。
- 国公立大学・・・準公務員。平均年収は低め
- 私立大学・・・大学ごとに財務状況は異なる。有名大学は高年収
ここまで紹介してきた大学業界で語られる2項対立の考え方についても、国公立と私立で考え方が変わることは多いです。
例えば、私立大学のほうがより財務についてシビアになりますし、国立大学のほうがミッションの達成が重要視されます。
大学ごとの方針によりますが、国公立と私立では根幹が違うので、大きな違いが生じやすいことは理解しておいたほうがいいでしょう。
以下の記事でも、国公立と私立の違いは紹介しています。
【関連記事】私立・公立・国立 それぞれのメリット・デメリット
【関連記事】国立大学から私立大学に転職した事例!大学職員が年収アップする方法
【関連記事】私立大学から国立大学に転職した事例!30代大学職員転職のリアル
異動官職とプロパー職員がいる
国公立大学で働く場合に知っておいたほうがいいのが、異動官職とプロパー職員というキャリアの違いです。
- 異動官職・・・文部科学省採用の職員で、国立大学法人に異動になるケース。出世が早い
- プロパー職員・・・国立大学で採用。大学内や近くの関連機関のみの異動
異動官職(いどうかんしょく)は、「文科省の人」などと呼ばれることもあります。
所属は文部科学省であることが多く、キャリア形成の一環で国立大学に赴任します。赴任時は部長級・課長級であることが一般的で、40歳前後で課長になります。
プロパー職員は、大学職員の多くを占める国立大学と関連機関のみで異動する職員です。
課長級への昇進は50歳前後が一般的で、異動官職に比べると昇進スピードは遅めです。
異動官職は文部科学省での業務経験を持ち、優秀な職員も多いですが、暗黙知・現場主義的考え方を持たないこともあり、プロパー職員から否定的な考え方を持たれることも多いです。
面接官には異動官職として文部科学省から出向してきている人も多いため、文部科学省が掲げる政策などの知識をつけておくといいでしょう。
異動のスパンが長い・短いどっちがいい?
主に国公立大学では、2~3年ごとの部署異動が通例とされています。
様々な部署を経験してキャリアアップを目指すという考えと、長期間同部署にいると業者等との癒着が生まれるという考えから、2~3年で部署異動があります。
そんな大学内でも同一部署に5年以上いる職員もいれば、1年で異動になる職員もいます。
異動のスパンに関しては以下のような傾向があります。
- 情報システム系など専門性が高い部署は異動スパンが長い
- 異動スパンが短いのは、優秀ではない職員が多い
優秀な職員であれば上長が1年程度の短期間では異動させないという考えから、短期間で異動を繰り返す職員は「なにか問題があるのかな」と考えられる事が多いです。
- 異動スパンが短い・・・様々な部署を経験できる
- 異動スパンが長い・・・1つの部署でじっくり経験を積める
キャリアプランとして総合職の課長を目指すのであれば、短期スパンで異動を繰り返したほうが経験値を積めると思います。専門性を身につけるのであれば、1つの部署を長く経験したほうがよいです。
正規職員と非正規職員どっち?
一昔前までは、企画立案や統括などは正規職員が、定型的な業務は非正規職員が担うというイメージがありました。
しかし、昨今では正規職員以上に非定型的な業務をこなす非正規職員も増えています。
「特任専門職員」のような任期付きの役職で、情報システムの保守管理・産学連携の推進を行っている職員が多くいます。
専門性を持つ非正規職員では、給与や待遇面で正規職員に近づいていますが、雇用期間は有期です。
非正規職員は専門性があっても雇用のための予算がなくなれば雇用も打ち切られてしまう可能性が高いです。非正規職員にも魅力的な求人は増えていますが、雇用期限がある点については理解しておくべきです。
- 正規職員・・・無期雇用の安定感、人事異動に従う必要あり
- 非正規職員・・年収の高い専門職も増えている。雇用期間に期限あり
長期的に働く希望がある場合は、正規職員を目指すべきですが、非正規職員からの正規職員への登用を狙うということを考えてもいいかもしれません。
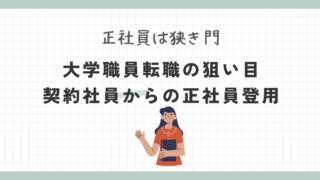
まとめ:仕事内容は2つの考えから整理しよう
大学職員の仕事でよく聞く、「どっち」の考え方を紹介してきました。
今回紹介した「どっち」については、大学や時代によっても考え方が変わっていきます。
極端な考え方を持つよりも、柔軟に考えて面接で答えられるようにしていくといいでしょう。
また、面接内での逆質問で面接官に聞いてみるのも面白いかもしれません。例えば、以下のような質問です。
- URAや教学IRなど、職員にも専門性が必要なケースが増えていると思いますが、貴学での職員教育の取組はありますか?
- 「規程主義と現場主義」のギャップを埋めるのにはどのような取組が必要だとお考えになるか伺いたいです。
- 私は〇〇のように考えますが、私立大学にない国立大学の強みはどんなお考えか知りたいです。
今回紹介した視点から、大学のホームページなどを見ると理解が深まるかもしれません。面接対策などの参考になれば、幸いです。
【関連記事】国立大学法人は統一採用試験・独自採用試験どっちが採用されやすい?
【関連記事】大学職員への転職サイト・エージェントおすすめランキング
【関連記事】大学の事務補佐員・技術補佐員の実際の仕事内容を部署ごとに紹介
【関連記事】大学職員は契約社員から正社員登用が狙い目!正規採用は狭き門
【関連記事】国立大学職員と公務員どっち?市役所や私立への転職・併願の事例も紹介