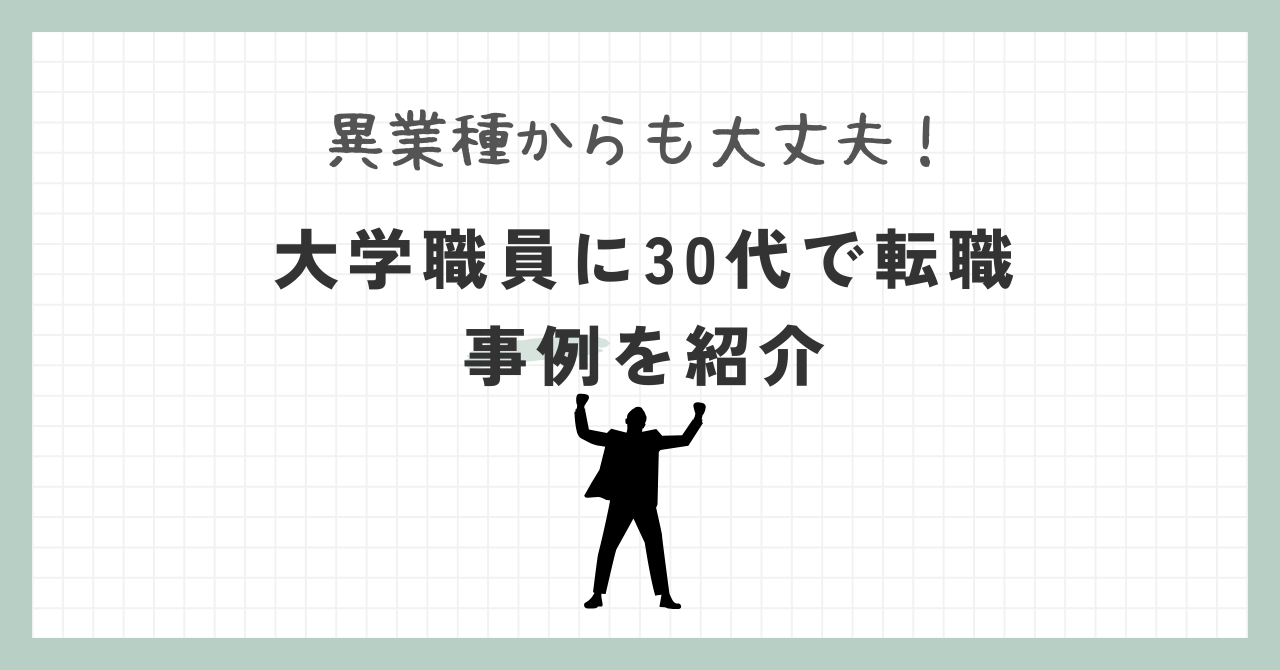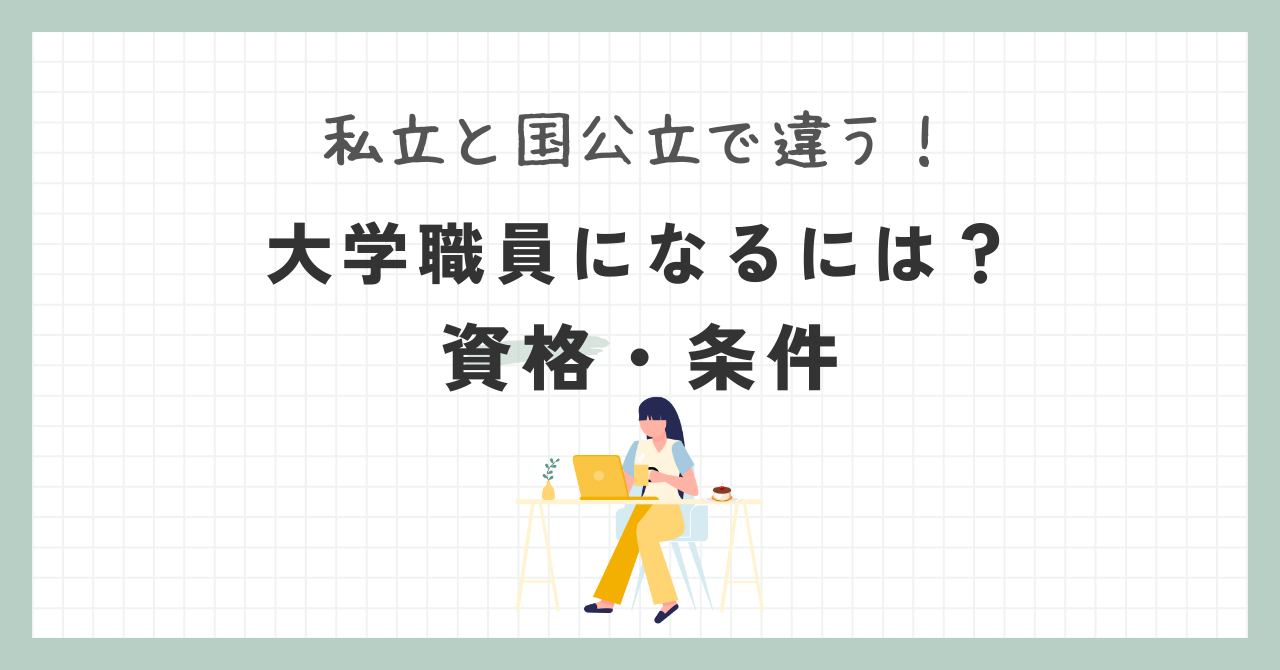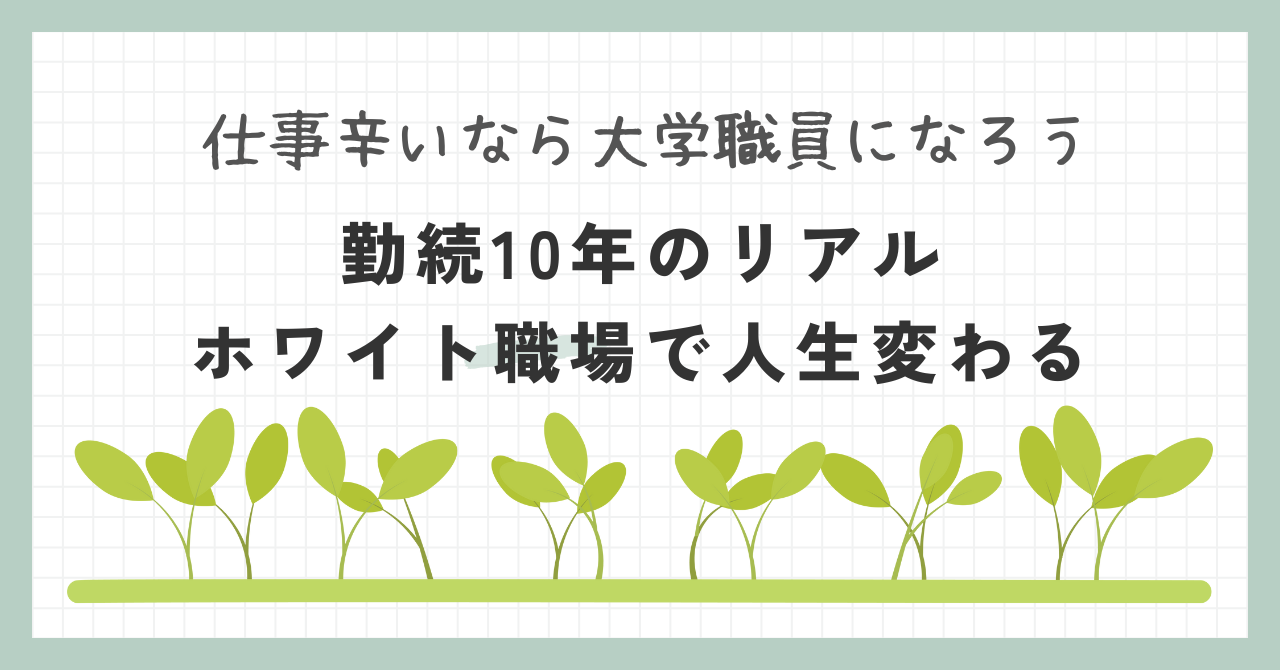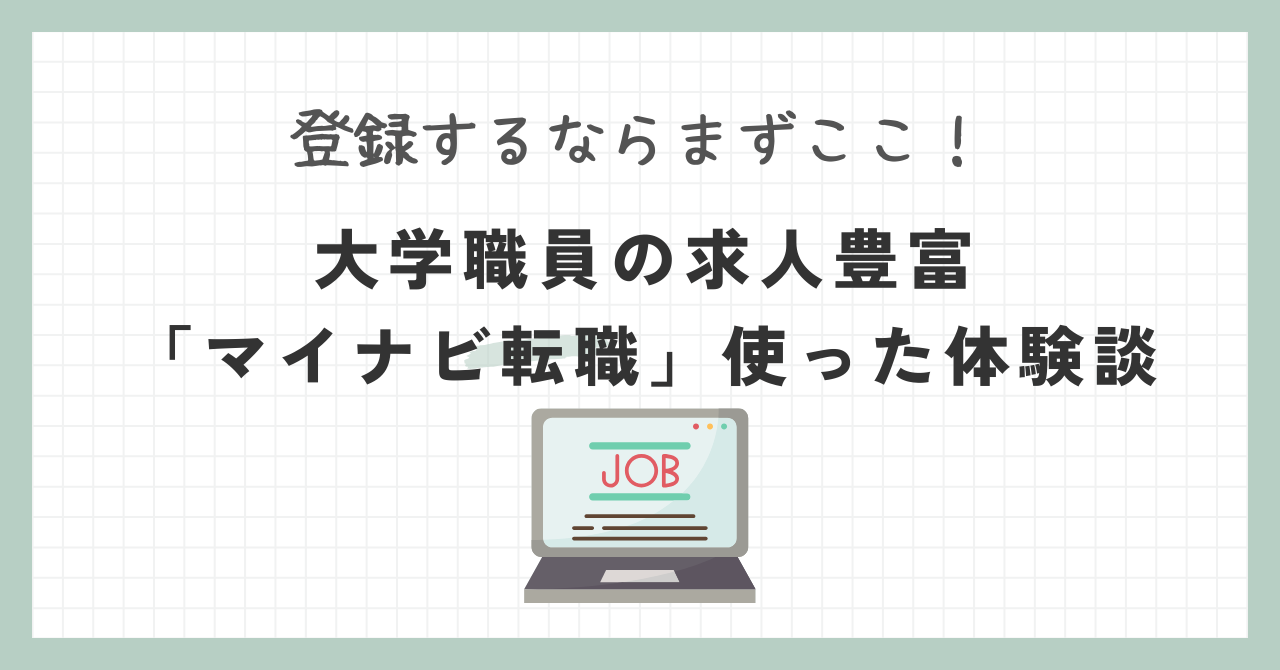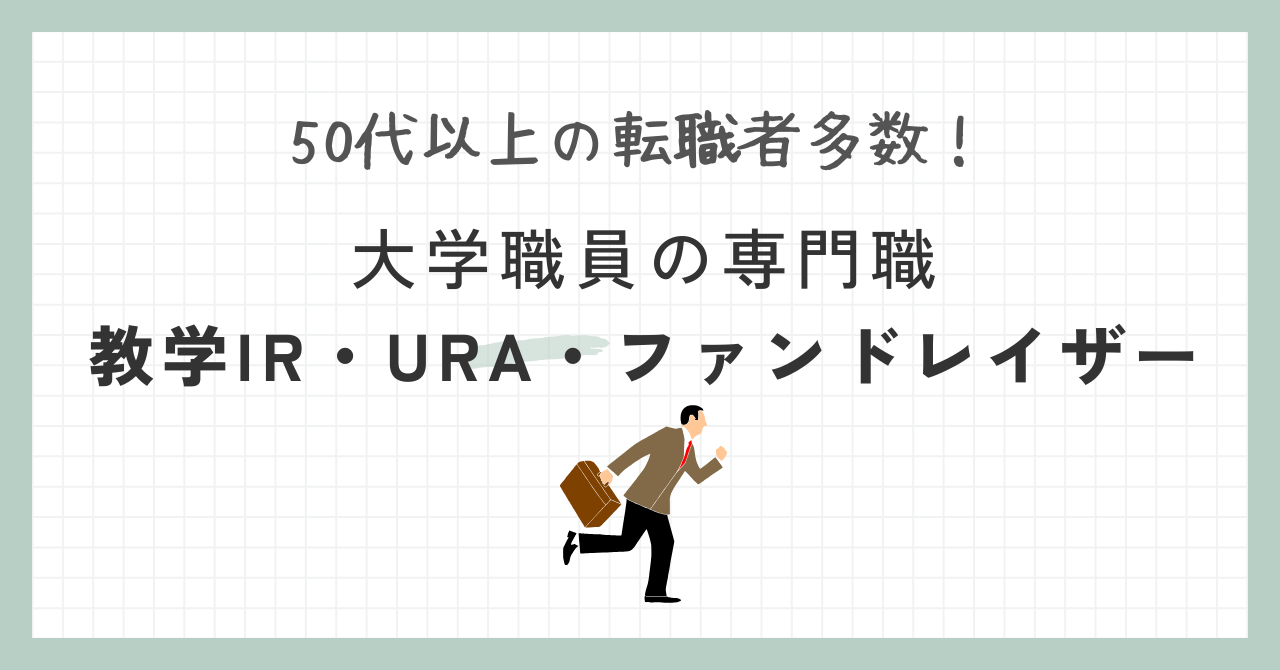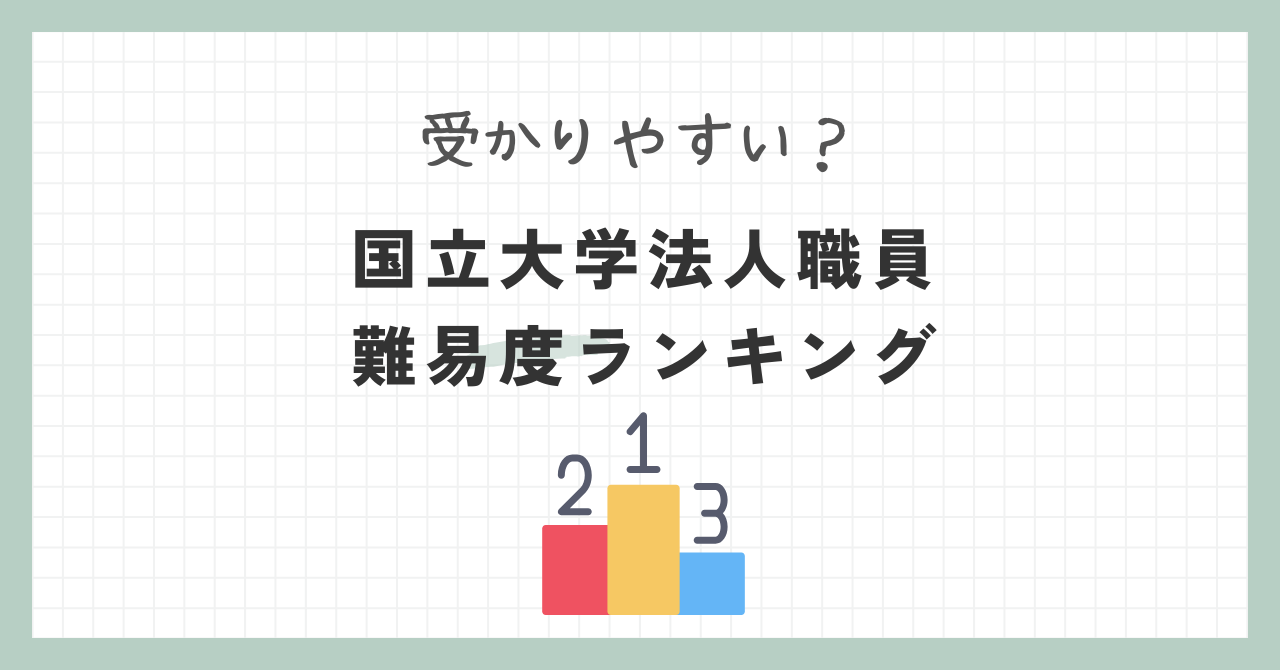【2026年版】大学職員への転職サイト・エージェントおすすめランキング
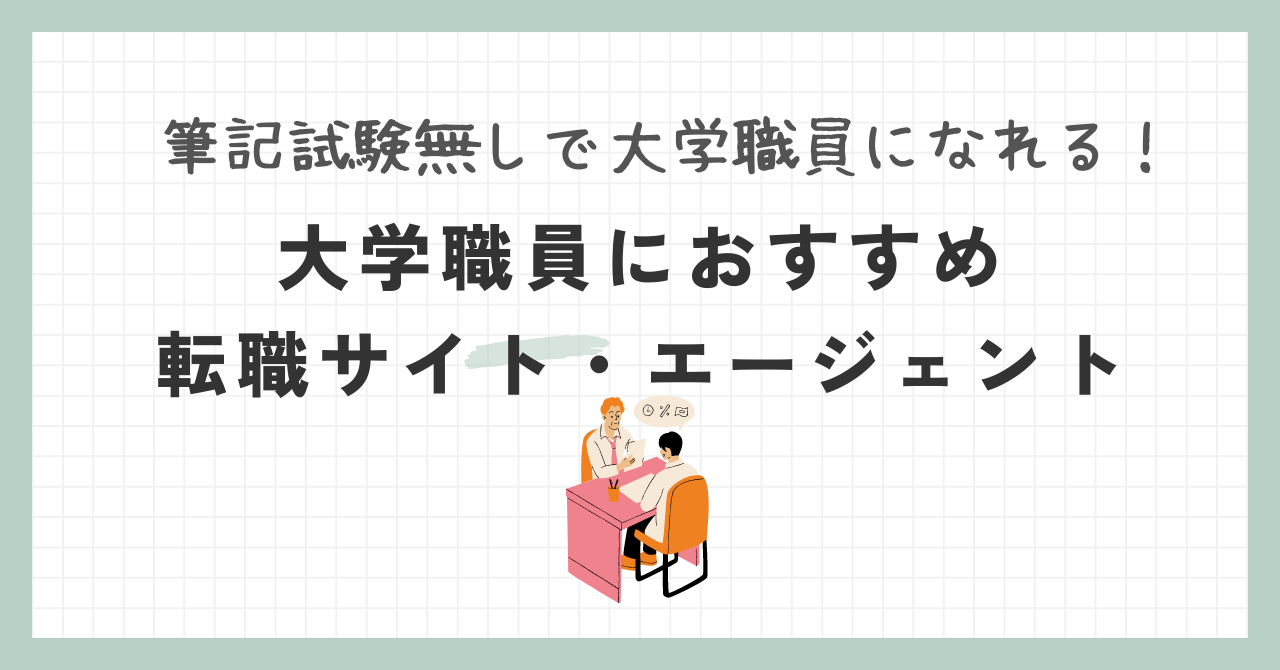
- 大学職員へ転職をしたい
- 大学職員の求人が多い転職サイト・転職エージェントを知りたい
こんなお悩みを解決する記事になっています。転職サイトが多すぎてどこに登録すればいいかわからないという方に、大学職員への求人の多いサイト・エージェントを紹介します。
- 大学職員への転職はマイナビ転職・リクナビNEXT・リクルートエージェント・dodaの4社でOK
- まれに求人がある転職サイト・転職エージェントも紹介
- 大学ホームページやハローワークも要チェック!
結論からいうと、マイナビ転職・リクナビNEXT・リクルートエージェント・dodaの大手4社に登録しておけば、多くの求人は網羅できます。
本記事では、転職するためにオススメの転職サイト・エージェントを紹介します。筆者の妻は、転職サイト(リクナビNEXT)を利用して大学職員の内定を得ていますので、参考になる情報をお届けできると思います。
私立大学だけではなく、国公立大学の求人も最近は見かけることがありますので、漏れずに登録しておきましょう。

大学職員への転職におすすめの転職サイト
大学職員になるための転職サイトで登録すべきは「マイナビ転職」「リクナビNEXT」です。
転職サイトは、求人が掲載されているサイトのことでエージェント等を通さずに直接大学にエントリーすることができます。
マイナビ転職・リクナビNEXTをおすすめするのは求人数が圧倒的に多いからです。
1位:マイナビ転職 求人掲載数No.1
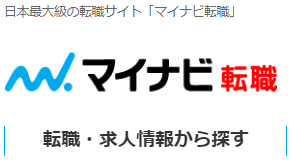
大学がまず求人を出すのが「マイナビ転職」です。
「マイナビ転職」は大学職員の求人が多いことに加えて、見やすいサイト設計も嬉しいポイントです。
ただ「大学」や「大学職員」で検索すると、「対象:大学卒業者」などの求人も引っかかるので、職種での絞り込みがオススメです。
「職種」→「公共サービス」→「学校法人職員」
求人が出たらすぐに応募できるように、会員登録を行っておくといいでしょう。
転職情報収集は無料の会員登録から
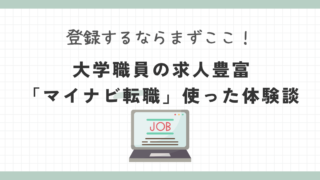
2位:リクナビNEXT マイナビにない転職求人あり
転職サイトの求人数は「マイナビ」と「リクナビ」の2強です。リクルート系列の転職サイトが「リクナビNEXT」です。
「リクルート」が強いエリアもあるため、「マイナビ転職」と合わせて「リクナビNEXT」も登録しましょう。
学習塾の求人や、事務職ではない技術職の求人が紛れていることもありますので、探すときには注意しましょう。
無料の会員登録で求人検索
番外編:狙う求人によって、確認すべき転職サイト
全員が登録すべきは上記の2サイトですが、番外編として2つのサイトを紹介します。
有名私立大学を狙うなら「リクルートダイレクトスカウト」
ハイクラス転職のスカウト型求人サイトが「リクルートダイレクトスカウト」です。有名私立大学は30代で年収1000万円を越えることがあり、高年収の職業と言われます。
高年収の有名私立大学を狙う方は「リクルートダイレクトスカウト」にも登録しておきましょう。
ただし、英語が堪能などの特筆した能力や、IT系やコンサルなど特殊な業務経験がないと、スカウトが届かないという状況になります。
契約社員やアルバイトから始めるならハローワーク
契約社員の募集は、大学ホームページとハローワークだけという大学もあります。
近年、大学では人件費を抑えるために、契約社員・派遣社員を増やしています。正社員登用もよくあるので、「契約社員から正社員を目指す」というのもおすすめしています。
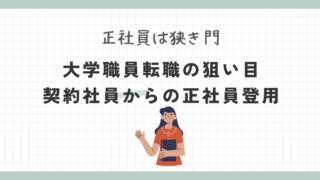
大学職員への転職におすすめの転職エージェント
転職エージェントは、自分がサイト内で求人を探すのではなく、エージェント(担当者)から求人を紹介してもらえる転職サービスです。
転職エージェントについても、やはり大手に求人が集まります。
1位:リクルートエージェント 随一の求人力

やはり、転職エージェントでもリクルートが強いです。
「リクルートエージェント」には、非公開求人が多数あります。
大学職員は採用倍率が高くなる傾向があるため、転職エージェントを利用して能力がある人のみを密かに集めている大学もあります。
「大学職員」に絞って転職活動をしていても、別の職種を頻繁に紹介してくる担当者が付く場合もありますので、注意しましょう。
大学職員への求人を持っているリクルーターと繋がるためにも必須の転職エージェントといっていいでしょう。
無料登録でスカウトを待ちましょう
2位:doda 転職エージェントの雄

転職エージェントの中では、リクルートに続くのは「doda」です。「doda」は担当者の質に定評があります。
リクルートに比べて、丁寧に自分にあった仕事を紹介してくれます。
全国的には有名ではない優良な大学等については、dodaからの紹介という可能性が高そうです。最近では、dodaで東京大学の求人募集も行われていました。
親切なリクルーターとの面談から
3位:マイナビエージェント 安定のマイナビの求人力

マイナビ系列の、「マイナビエージェント」にも登録しておくといいでしょう。やはり、マイナビ系列にも他の転職エージェントにはない求人案件があります。
1つの転職エージェントでしか扱っていない求人もあるため、全て登録するというのが基本的な考え方になります。
ただし、リクルートエージェント・dodaに比べると大学職員の求人は少なそうです。
マイナビならではの求人も
大学職員への転職活動の進め方

「今すぐ転職したい!」という方は、転職サイト・転職エージェントに登録すればいいですが、「とりあえず情報収集から」と考えている方もいると思います。
自分の状況にあわせて、進めていきましょう。
ステップ1 大学職員の仕事の情報収集
- 大学職員の仕事に興味を持ち始めた
- とりあえず転職活動をスタートさせたい
情報収集を行うにも、転職サイトには登録しておきましょう。会員だけにしか見られない情報もあるからです。情報収集の段階では「マイナビ転職」と「リクナビNEXT」だけでもOKです。
この時点で、エージェントに登録してしまうと、余計なメールや面談が増えて、思うような転職活動が行えなくなることもあります。
ステップ2 具体的な働き方をイメージする
例えば、以下のように働き方をイメージしましょう。
- 英語力を活かして、国際交流や留学生対応の仕事がしたい
- 契約社員も含めて、求人を探したい
情報収集が進むと、「大学職員への転職」の課題が見えてくるはずです。この時点で、大学職員への転職は難しいと考える人もいるはずです。
- 自分の年齢では、正社員の求人がほとんどない
- 居住地から通える大学は限られる
- 英語が得意なので、ハイクラス転職が可能かもしれない
- 筆記試験を受けられる20代のうちに、国立大学に挑戦したい
契約社員やアルバイトも視野にいれるのであれば、地元のハローワークにも登録して、多くの情報を入手するようにしましょう。
希望の大学が数校に絞られる場合は、大学ホームページに求人情報がないかもチェックしましょう。大々的に募集を行わず、ホームページのみで求人募集を行っているケースもあります。
都市圏在住などで多くの求人を比較したい場合には、スカウト型やエージェント型の転職サイトに登録すると、非公開求人が見つかる可能性が高くなります。
無料登録でスカウトを待ちましょう
情報収集をしていて、国立大学法人の筆記試験に挑戦したいという方は、通信講座を利用すると効率的に知識を定着させることができます。

ステップ3 興味がある案件には、ひたすら応募
- 大学職員への転職意思が固まった
- 自分が求める求人(勤務エリア・年収・職種)が説明できる
ステップ3まで来たら、「doda」「マイナビエージェント」にも登録しましょう。非公開求人も含めて紹介を受けることができます。
転職の意思が固まったら、あとは求人情報を集めて、選考を受けていくフェイズに入ります。
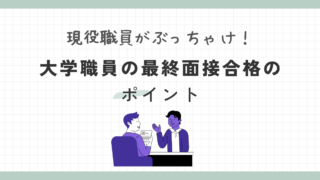
まとめ:転職活動はサイトへの登録・情報収集から
大学職員への転職にオススメの転職サイト・転職エージェントを紹介してきました。働き方によって、登録・閲覧するべき転職サイトが変わります。
- 全員 →「マイナビ転職」「リクナビNEXT」「リクルートエージェント」「doda」「マイナビエージェント」
- 特定の大学 →「大学のホームページ」
- 契約社員 →「ハローワーク」
- スキルでアピール→「リクルートダイレクトスカウト」
まだ、大学職員の仕事への情報収集が不足している方は他の記事も参考にしていただければと思います。
近年では、国立大学も社会人採用を増やしているので、国立大学も検討してみるのがおすすめです。
【関連記事】無料!国立大学法人・公務員を目指す人必見の公務員転職ハンドブックを紹介
【関連記事】国立大学法人は統一採用試験・独自採用試験どっちが採用されやすい?
【関連記事】国立大学法人で受かりやすい穴場はどこ?難易度ランキングも解説