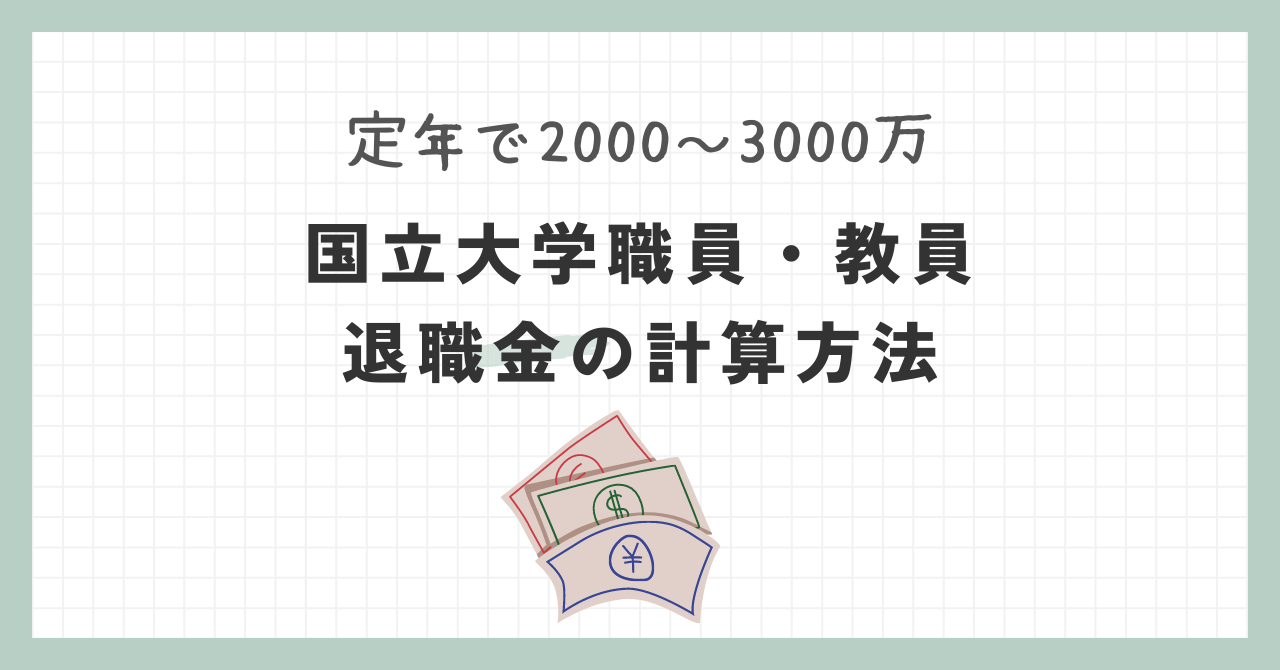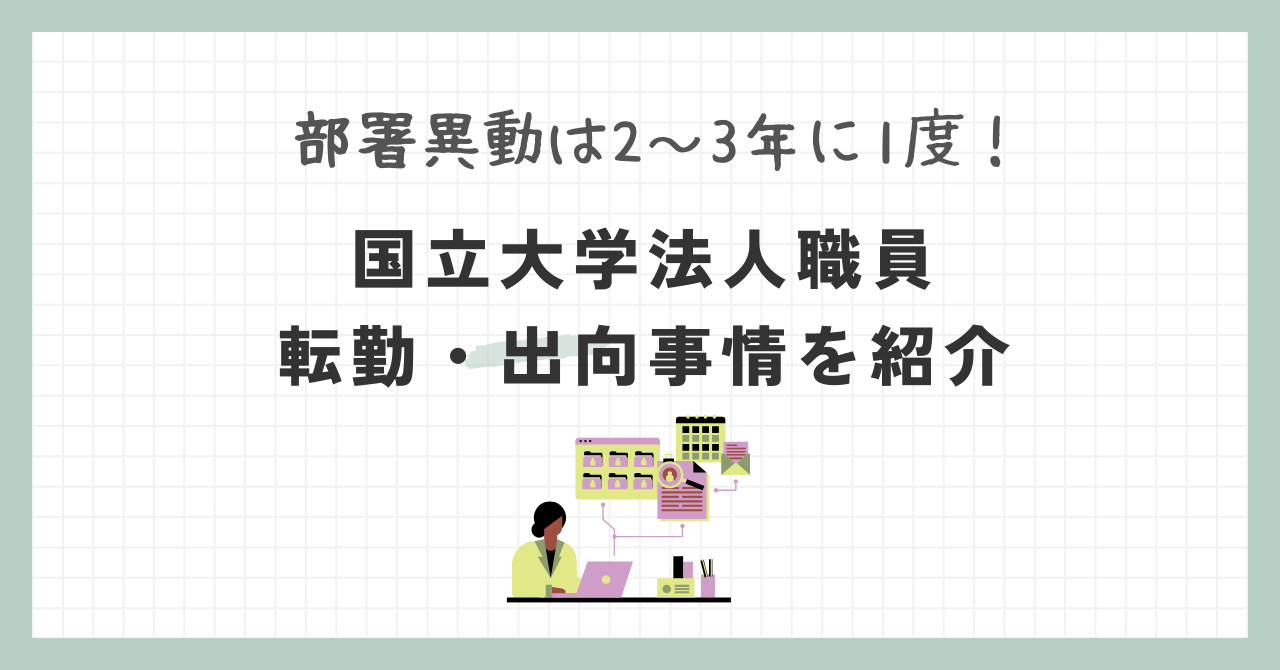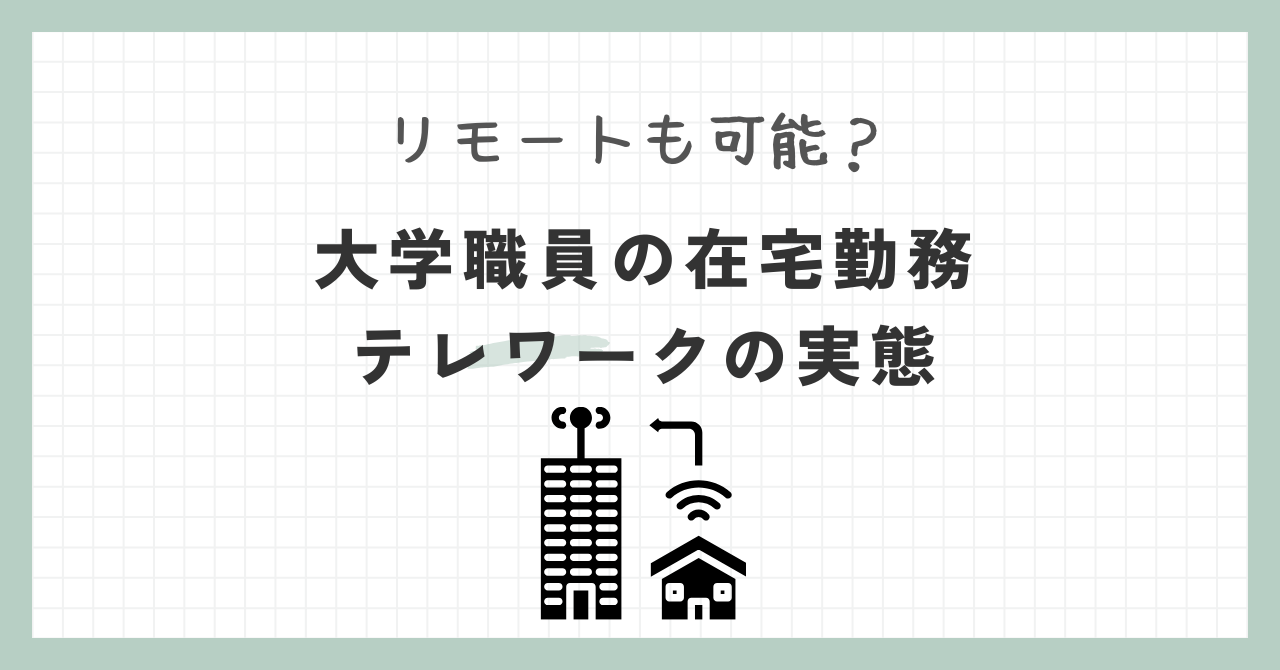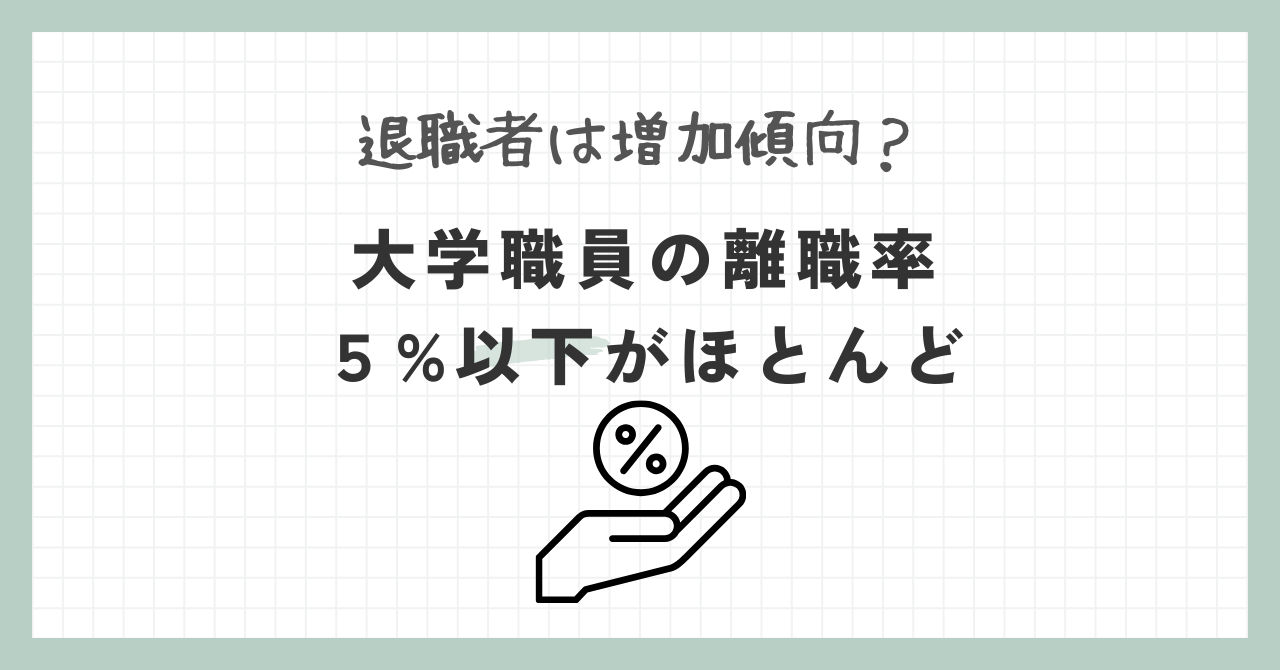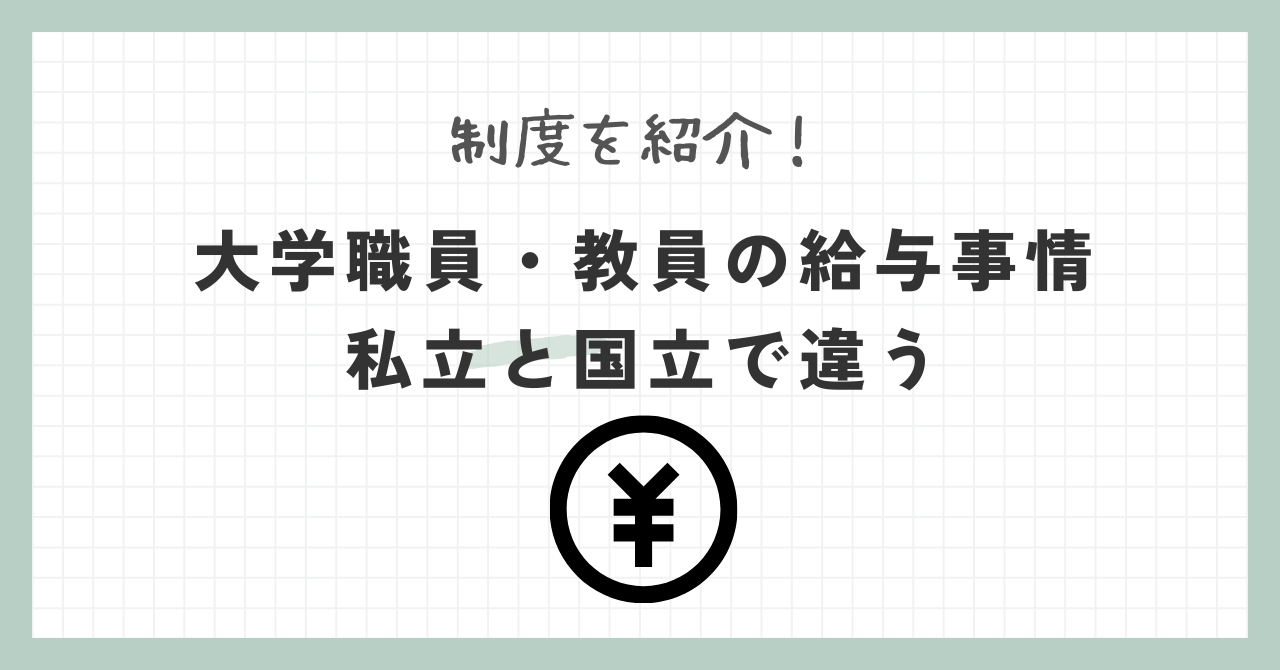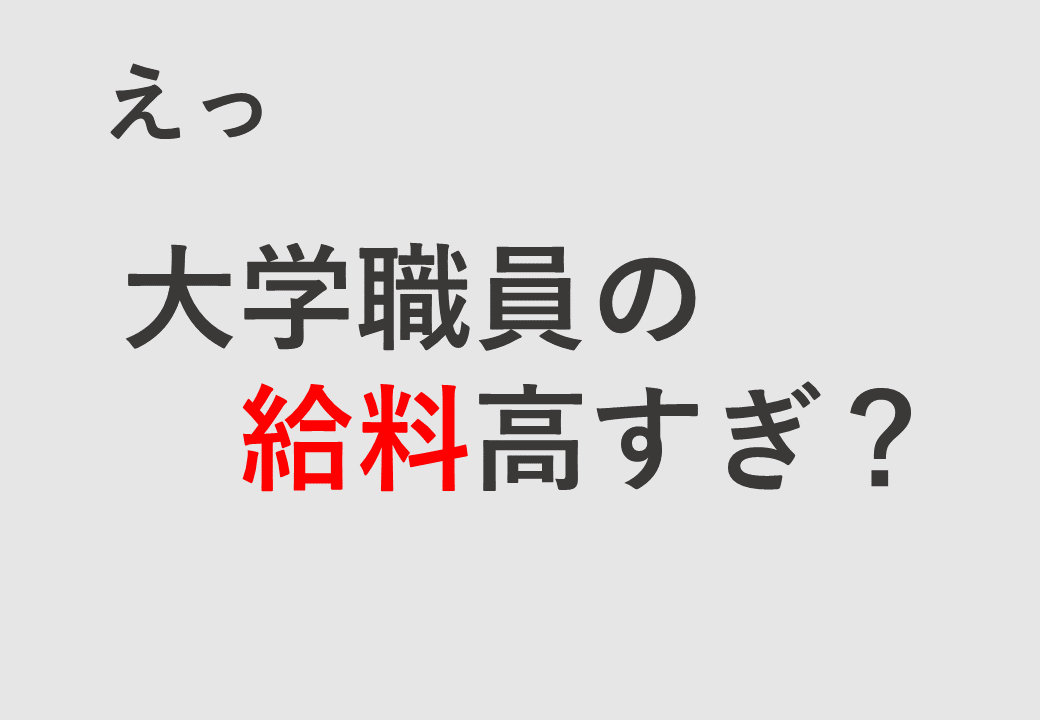大学職員のリストラは今後増える?安定した職場の将来性を解説
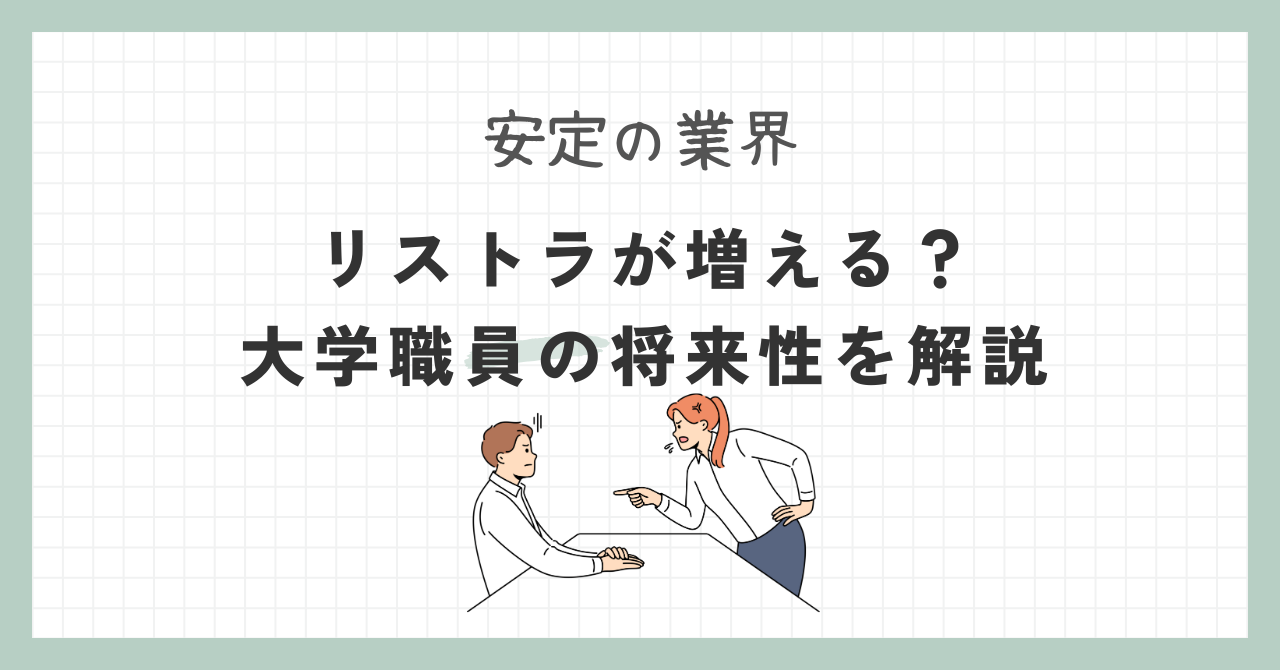
大学職員は景気に左右されにくい安定した職業です。
安定しているのは、大学が「国による補助金等が整備されている」「参照障壁が高く、競合が増えにくい」組織だからです。
一方で、近年は入学者募集を停止する私立大学が増えてきて、将来性を不安に感じる人も多いでしょう。
- 大学職員は安定した職業。5つの要素から安定性を解説
- 大学の将来性には不安もあるが、国立や有名私立大学はしばらく安泰
- 運営費交付金があるため、リストラが行われる可能性は低い
大学職員の将来性やリストラの可能性について、現役職員が解説していきます。
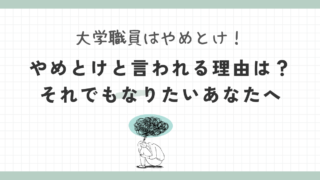
大学職員のリストラが増える可能性は?
近年では、「入学者募集停止」というニュースをよく聞きます。
- 恵泉女学園大学(2024年入学者から)
- 神戸海星女子学院大学(2024年入学者から)
- 上野学園大学(2021年入学者から)
- 広島国際学院大学(2020年入学者から)
少子化の影響で、定員割れの大学が増えている状況です。大学職員の仕事・待遇への影響を気にする人は多いでしょう。
経営が悪化している私立大学はボーナスカット・部署異動などが行われます。
しかし、すぐにリストラとはなりません。日本の法律では簡単に解雇できないため、新規採用の停止や賞与カットなどの対策を行うことになります。
経営が悪化している私立大学の一部は、税金が投入されて公立大学になっているケースもあり、経営悪化がすぐにリストラには繋がらないのが大学業界です。
続いて、大学職員の職場環境が安定していると言われる理由を解説していきます。
大学職員の仕事が安定している理由
一般的に仕事の安定性は、経営状況の安定を指します。経営が安定していれば、人員整理やボーナスカットなどを行う必要がなく、安定した雇用環境・待遇を維持できるからです。
大学の経営状況は、多くの民間企業に比べると安定しています。
「国による補助金等が整備されている」「参入障壁が高く、競合が増えにくい」という理由から説明できます。
学校法人への補助金等が整備されている
大学は「学校法人」が運営しています。学校法人は「よりよい教育を行うため」に設置された機関です。
教育を行うために、国からの補助金が整備されており、景気に経営が左右されにくい特徴があります。
受験生・学生がいる限り、円安や物価高という状況でも経営が傾くということは考えにくいです。
大学経営の失敗で学生が不利益を被る状況にならないように、国が後ろ盾としてサポートしているイメージです。
参入障壁が高く、競合が増えにくい
大学は参入障壁が高く、競合が増えにくい環境です。
数年の間に同じ地域に新しく大学がいくつも開設されたという話は聞きませんよね。大学の設立には文部科学省の認可が必要となり、多額の資金も必要になります。
競合サービスの登場で倒産に追いやられる企業も少なくない中、「大学は高い参入障壁に守られている」と考えていいでしょう。
5つの安定要素
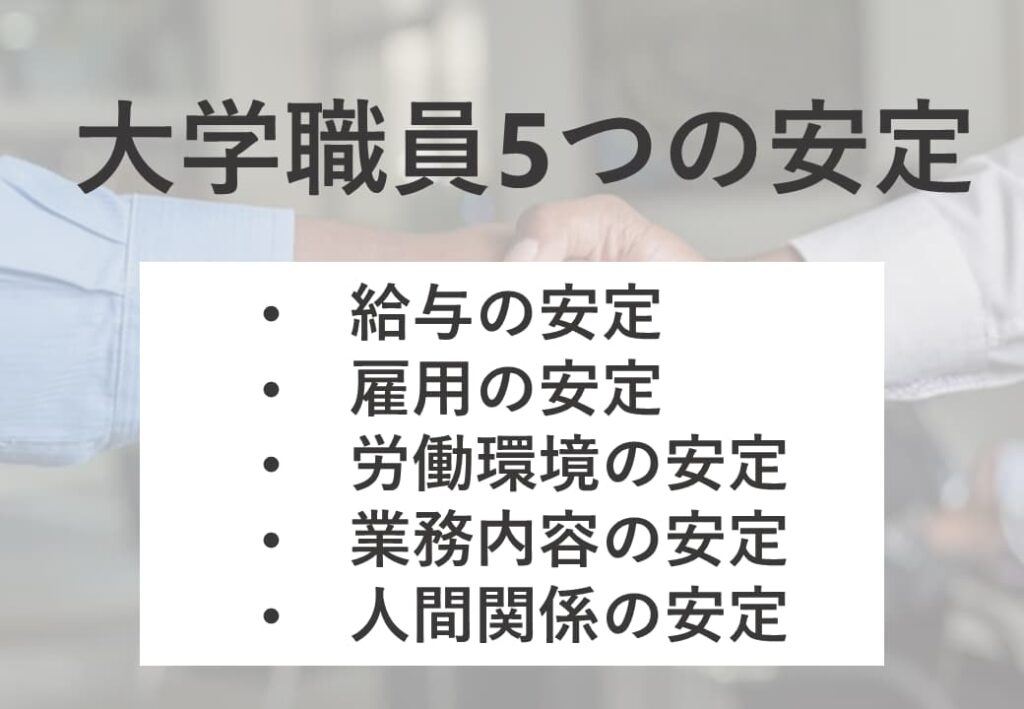
民間企業と比較して感じる「大学の安定」を5つの点で紹介します。
- 給与の安定
- 雇用の安定
- 労働環境の安定
- 業務内容の安定
- 人間関係の安定
給与の安定:国家公務員踏襲の給与体系
国立大学は元国家公務員のため、公務員の給与体系を踏襲しています。
2023年以降、人事院勧告による大幅な賃上げが続いており、国立大学の教職員も給与が増額されています。
※予算不足で賃上げできない大学がある点については後述。
私立大学では経営が苦しくなり、賞与がカットされた話を聞いたことがありますが、一定以上の規模の大学では、しばらく問題ないでしょう。
18歳人口減少による将来性の不安はありますが、短期的に大学の教職員の給料が下がる可能性は低いです。
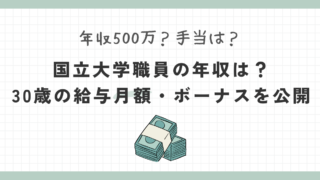
雇用の安定:経営状況が安定しており、リストラが不要
大学職員は雇用環境も安定しており、リストラや人員整理ということは考えづらいです。
大学経営が景気による影響を受けづらいこと、学校法人には国からの補助金等があることが理由です。
経営状況の悪化や、国からの補助金の減額があっても、まずは新規採用数を絞ることや職員の非常勤職員化で調整するので、現職に影響が出るのは先になります。
民間では、大企業でも解雇や早期退職の募集が行われている状況です。財政破綻する市もある状況で、大学職員の安定性は高いと言えます。
ただし、長期的には18歳人口が減り、受験料収入が減ることは間違いありません。実際に、4人でやっていた仕事を現在は3人でやっているという部署はあります。
労働環境の安定:ワークライフバランスを重視できる
大学職員はワークライフバランスを重視できる環境です。ライフプランに応じて働き方を変えられる制度が整っています。
病気・育児・介護などに関する休業・時短勤務制度を利用しやすいため、育児休業と復帰を繰り返して、3人の子供を育てながら管理職になっている女性職員もいます。
経営(収入)が安定しているため、職員を休ませる余裕があるということでしょう。
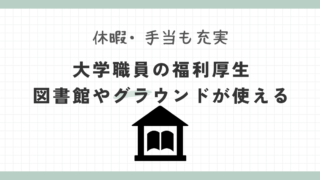
業務内容の安定:大きく仕事内容が変わることはない
仕事内容が安定しているのも大学職員の特徴です。
大学事務職員の仕事は「総務・人事系」「学務・教務系」「財務・会計系」のいずれかがメインです。
参考:大学職員の職種の分類は「事務8割」「技術1割」「図書1割」
「より良い教育を提供する」のが、学校法人の目的ですから、目的外の職種への異動は考えにくいです。
民間企業では、経営を続けるために業態(柱となる売上)をシフトしている企業は多いです。
- ワタミ(飲食業界→介護業界)
- トヨタ(自動車メーカー→カーローンによる金利収入)
- オルビス(店舗販売→ネット販売中心)
会社が力を入れる分野に合わせて、社員が働く場所も変わっていくことはよくありますが、大学職員が全く違う業界の仕事を行う可能性は低いです。
人間関係の安定:関わるのは教員と学生が中心
公的機関で働く大学職員・大学教員には態度のムラがない人が多く、安定した人間関係が築けます。
大学に関係する人は心穏やかな人が多いので安心して働くことができます。
常にノルマに追われて、業績に左右される民間企業とは異なる環境だといえるでしょう。安定した対人関係の中で仕事ができるのは恵まれていると思います。
恵まれている大学ですが、中には人間関係にストレスを感じるという人もいます。

大学職員の将来性は?

大学職員の将来性について、現場で働いて感じること紹介します。
限界の国立大学
国立大学の運営が厳しいという話は、近年ニュースでよく聞くようになりました。以下の書籍などでよく状況がわかると思います。
- 和式トイレを洋式に変える費用がない
- 耐用年数を超えた医療機器を使い続けている
- 築40年の外壁にヒビが入り、みすぼらしい建物
どこの国立大学も多かれ少なかれ、上記のような危機的な状況にあります。人件費や光熱費の高騰でとても設備や修繕にお金を回せる状況ではありません。
各地の現役大学教員・医師などが限界を訴え、少しづつ運営費の配分が増やされています。
現役大学職員の筆者として率直に感じることは以下の通りです。
- 建物・設備の老朽化は深刻。人件費・光熱費の高騰も仕方ない
- 一方で、人員削減・経費削減・効率化は改善の余地あり
【人員削減・経費削減できない理由】
例えば、学生支援の業務を4人で担当している部署があるとします。
AIを駆使したり、教員・学生に協力してもらうことで人員を1人減らすことは不可能ではありません。
しかし、1人雇用を減らしたとして
- 自分の給料は上がらない、特別評価されるわけでもない
- 来年も当然に3人で業務を行うことになる
- 人が減った分、休暇は取りにくい
このようにデメリットしかないので、みんな「4人で限界です」と言っているのです。どこの部署も同じなので、一向に効率化が進みません。
大学全体で人員削減が成功したとしても、「予算減らして運営できるじゃん」と国が判断すれば交付金の額が減るだけです。
このような構造から、真に必要な人員削減を行わないのが実態だと考えています。
確かに国立大学には厳しい時代ですが、民間企業よりはマシだというのが筆者の見解です。
本当に厳しく、過労死する大学教職員が増えれば、予算も確保されると思います。
AIの普及による将来性の不安
2020年代以降、一般人が使えるAIが増え注目を浴びています。AIに仕事を取られる仕事の代表的なものとして「事務職」が挙げられます。
実際に、書類作成やデータの取りまとめなどは生成AIの影響を受けるでしょう。
公務員の仕事と比較されることがありますが、大学職員のほうがAIに仕事を取られる可能性は高いと考えています。
- 大学職員・・・教員が学生サービスを行えるため、職員の必要性は薄い
- 公務員・・・・単純な事務仕事以外にも福祉事業・災害対応・観光などマンパワーが必要な分野は多い
これから大学職員として働く場合には、「大学職員をやめても働けるスキル」を身につけることは必須になるでしょう。
10年程度は大きな変化はないと思いますが、「人口減少」「AI普及」という2つの脅威がある点は理解しておくべきです。
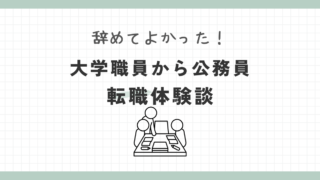
公的研究・医療の社会的意義
大学職員の将来性に不安を感じた方もいると思いますが、民間企業にはない社会的意義が大学にあることも現場では感じます。
- 利益追求の民間企業ではできない基礎研究を行える
- 学生が減っても、附属病院の収入がある
コストパフォーマンスが悪い研究も大学では行えます(近年、風当たりが厳しいですが)。地道な研究が大きな成果を生み出すこともある以上、公的研究は必要とされ続けるでしょう。
また、医療分野は今後もマンパワーが必要な業界なので、附属病院に大学職員が多く配置されるということもあるかもしれません。
「ホワイト職場だから安心」と思うのは危険ですが、研究力のある大学の将来性について過度に心配する必要もないように思います。
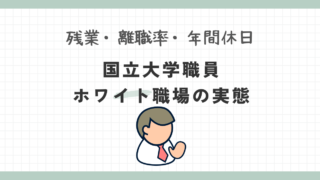
国立大学と私立大学の違い
「国立大学より私立大学のほうが待遇がいい」という意見があります。
確かに、公務員に近い待遇の国立大学職員に比べて、私立大学職員の方が高年収の傾向があります。
- 国立大学職員・・・元国家公務員、国立大学法人として独立行政法人が運営
- 私立大学職員・・・民間の学校法人が運営し、教育・研究に特色がある
年収を始めとした待遇・福利厚生では、私立大学職員の方が人気がありますが、学生数減少・授業料収入減少の影響を受けやすいのも私立大学です。
年収が高いからと安心せずに、学生数減少などの影響を受けていないか、自身で確認することも必要です。
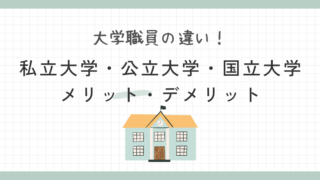
まとめ:将来性には不安もあるが、安定職種
大学職員は様々な要素から、安定している仕事といえます。経営状況が安定しているため、給与・雇用に関しては、不安になる必要はないと考えています。
また、大学職員としての安定を享受しながら資格勉強などを進めるのもいいかもしれません。国立大学職員になる方法を以下にまとめています。
| 国立大学職員 になる方法 | 統一採用試験 (33歳以下の人におすすめ) | 独自採用試験 (34歳以上の人におすすめ) |
|---|---|---|
| 受験対象者 | 35歳まで(令和8年試験から) | 一定期間の社会人経験など、大学による。 |
| 試験日 | 筆記:6月~7月 面接:8月 | 6月~9月頃が多い |
| 筆記試験 | 教養試験(知能分野重視) | 適性試験程度、課さない大学もある |
| 書類選考 | 原則なし | 書類で半分以下に絞られる |
| 倍率 | 10~20倍程度 | 30倍以上の高倍率 |
| 求める人材 | 新卒・第二新卒がメイン 35歳までの若手を採用 | 大学運営に活かせる社会人経験 専門資格・スキルが必須なことも |
| 難易度 | 低め(誰にでもチャンスあり) | 高い(資格・経歴が必要) |
| 対策 | 3ヶ月以上かけて筆記試験対策を! 若いほど有利なので早めに受けたい | 募集が大学ごとのため、情報収集必須 公務員や常勤登用を狙うのも選択肢に |
| 関連記事 | ・法人試験におすすめの参考書 ・法人試験におすすめの通信講座 | ・公務員転職ハンドブックで情報収集を! ・契約社員から正社員登用の事例紹介 |
【関連記事】大学職員になってよかった!10年勤めた現役職員の変化
【関連記事】国立大学法人の独自採用試験とは?倍率や採用のコツを現役職員が解説
【関連記事】大学職員の仕事のやりがい・魅力は?現役職員に聞いた事務職のやりがい